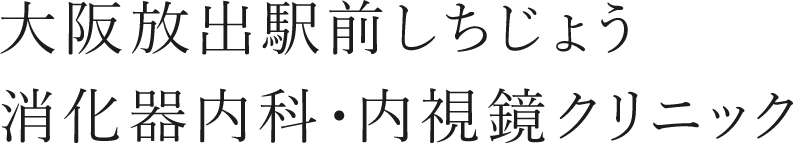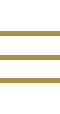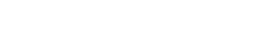食欲がない(食欲不振)
 食欲不振とは、「お腹が空かない」「食べたい気持ちにならない」「決まったものばかり食べる」「食べたい気持ちはあるのに食べられない」といった状態を指します。
食欲不振とは、「お腹が空かない」「食べたい気持ちにならない」「決まったものばかり食べる」「食べたい気持ちはあるのに食べられない」といった状態を指します。
原因はさまざまで、
- 消化器や内臓の病気
- 風邪や感染症
- 強いストレスや生活習慣の乱れ
- 薬の副作用
- 栄養バランスや体調不良、加齢
などが挙げられます。
私たちは食事から摂る栄養素によって生命活動を維持しています。食欲不振が続くと必要な栄養素を摂取できず、体力や免疫力の低下につながります。
「疲れているだけだろう」「そのうち戻るだろう」と放置せず、食欲不振が長引く場合は一度ご相談ください。
食欲が出ない原因
以下が食欲不振の主な原因です。
消化器疾患
- 胃がん:がんが作る「サイトカイン」という物質によって胃の働きが低下し、食欲不振を引き起こすことがあります。
- 慢性胃炎:胃の消化機能が落ち、食欲不振になることがあります。萎縮性胃炎の場合はピロリ菌の関与が疑われます。
- 胃・十二指腸潰瘍:胃の中に食べ物が残っているような感覚があり、食欲が減退します。
- 膵臓・肝臓・胆のうの病気:消化に関わる臓器の異常が食欲不振の原因となります。
全身性疾患
- 甲状腺機能低下症:ホルモン分泌の低下により食欲が落ち、食べていないのに体重が増えることもあります。
- 糖尿病・腎不全・心不全など:慢性疾患の影響で全身的に食欲が減退することがあります。
- 感染症:風邪やインフルエンザなどでも一時的に食欲が落ちます。
精神的要因・生活習慣
- ストレス:職場・家庭などの強いストレスで自律神経の働きが乱れ、副交感神経が抑制されて食欲が低下します。
- 生活習慣の乱れ:睡眠不足、運動不足、過度の飲酒などにより自律神経が乱れ、食欲が減退します。
薬の副作用
- 抗がん剤、抗生物質、一部の降圧薬や鎮痛薬などが食欲不振の原因になることがあります。
受診をおすすめするケース
風邪や一時的な疲労で食欲が落ちても、数日で回復する場合は大きな心配は不要です。
しかし、以下のような場合は早めに医療機関を受診してください。
- 食欲不振が 2週間以上続く
- 体重が急に減ってきた
- 食べても味がしない
- 吐き気・嘔吐・胃痛や腹痛を伴う
- 高齢者で食欲不振が続いている
- 発熱・寝汗・倦怠感がある
- 血便や黒色便、黄疸がある
これらは消化器がんや全身性の病気のサインである可能性もあります。
食欲不振の検査
 当院ではまず問診で、症状が始まった時期・食事内容・服薬歴・既往歴などを伺います。
当院ではまず問診で、症状が始まった時期・食事内容・服薬歴・既往歴などを伺います。
そのうえで必要に応じて、以下の検査を行います。
- 血液検査:貧血・肝腎機能・甲状腺機能・炎症反応などを調べます
- 腹部超音波(エコー)検査:肝臓・胆のう・膵臓などの異常を確認します
- 胃カメラ:胃炎・胃潰瘍・胃がんの有無を詳しく観察します
- 大腸カメラ:大腸がんや炎症性腸疾患が疑われる場合に実施します
当院では、熟練の消化器内視鏡専門医が苦痛を抑えた胃カメラ・大腸カメラ検査を行っていますので、安心してお受けいただけます。
食欲不振の治療
検査で原因が特定できれば、それに応じた治療を行います。大きな異常が見つからない場合でも、生活習慣の改善やストレスマネジメントの工夫を行うことで症状が改善することがあります。
体重減少
 体重減少とは、半年間で元の体重から5%以上減った状態を指します。
体重減少とは、半年間で元の体重から5%以上減った状態を指します。
たとえば60kgの方であれば、3kg以上の減少が目安となります。単なる「痩せた」とは異なり、肥満の方が意識的に減量した場合は体重減少には含まれません。
体重減少は、食事から摂るエネルギーと使うエネルギーのバランスが崩れ、エネルギー不足の状態を反映しています。また、私たちの身体の半分以上は水分でできているため、脱水状態によっても体重は減少します。
体重がどのくらい減ったら注意が必要?
体重減少が進行し、元の体重から10%以上、あるいは半年以内に5%以上減っている場合は、病気が背景にある可能性があります。「年齢のせい」「食欲が落ちているだけ」と自己判断せず、早めに検査を受けて原因を調べることをおすすめします。
体重が減る原因
体重は、摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスを反映する重要な指標です。
体重減少は、食事からのエネルギー摂取が低下した場合や、身体活動や代謝の亢進により消費エネルギーが増えた場合、あるいはその両方によって生じます。
摂取エネルギー減少の原因
- 食欲不振(胃がん・慢性胃炎・ストレスなど)
- 嚥下障害(飲み込みにくさ)
- 胃腸の疾患(潰瘍、炎症性腸疾患など)
- 糖尿病による消化不良
消費エネルギー増加の原因
- 運動量の増加
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- 悪性腫瘍による消耗
栄養不足
-
- 偏った食事
- 嚥下障害・虫歯などで十分に噛めない
→ 定期的な歯科検診も体重減少予防に役立ちます。
消化不良・吸収不良
摂取した食べ物は胃酸や消化酵素で分解され、小腸で吸収されますが、胃腸の疾患によってこの機能が低下すると体重減少につながります
代謝・内分泌異常
- 糖尿病:インスリン不足でブドウ糖が利用できず、体重減少・多飲多尿・口渇・高血糖などが出現
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病):代謝が過剰になり、食べても体重が減る
- 褐色細胞腫(まれ):副腎腫瘍によって体重減少・頭痛・吐き気が起こる
炎症性疾患などによるエネルギー消耗
- 関節リウマチや結核などの炎症性疾患
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- がんによる悪液質(全身の消耗)
加齢による影響(サルコペニア・フレイル)
- サルコペニア:筋肉量の減少で筋力や身体機能が低下
- フレイル:加齢に伴う身体的・精神的な衰え
→ 筋肉は水分を多く含むため、筋肉減少は脱水リスクも高めます。栄養と運動の両立が予防に不可欠です。
食欲不振、体重減少でお悩みの方は大阪市鶴見区の当院へ
 当院では、食欲不振や体重減少の原因を正確に調べるために、患者様の症状に合わせて 胃カメラ検査・大腸カメラ検査・腹部超音波検査 などを行っています。
当院では、食欲不振や体重減少の原因を正確に調べるために、患者様の症状に合わせて 胃カメラ検査・大腸カメラ検査・腹部超音波検査 などを行っています。
「最近食欲がない」「体重が急に減ってきた」など、気になる症状がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。