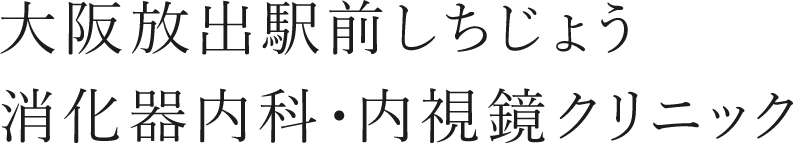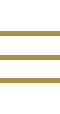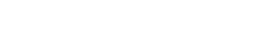げっぷがよく出る原因は?
病気のサイン?
 「げっぷが頻繁に出て悩んでいる」という方は、次のような原因が考えられます。
「げっぷが頻繁に出て悩んでいる」という方は、次のような原因が考えられます。
げっぷが増加している場合は、食道や胃の異常が疑われることがあります。症状が続くときは、胃カメラ検査などの精査を受けることを推奨します。
早食い・炭酸飲料の飲みすぎ
食事を早く摂ると、食べ物と一緒に多くの空気を飲み込んでしまい、胃に空気がたまりやすくなります。
炭酸飲料やビールなどの発泡性飲料も同様に、胃にガスが発生し、げっぷが増える原因となります。
→ ゆっくり食事する、炭酸飲料を控えることで改善する場合があります。
加齢
加齢に、食道裂孔ヘルニアや下部食道括約筋(LES)の機能低下が起こることがあります。
LESは胃と食道の境目にある筋肉で、これが緩むと胃酸や胃の空気が逆流しやすくなり、げっぷが増加します。
→ 高齢者だけでなく、肥満・妊娠・姿勢の影響でも起こります。
ストレス
ストレスや不安が強いと、無意識に空気を飲み込む「呑気症(どんきしょう)」が起こりやすくなります。
また、自律神経の乱れにより胃腸の働きが低下し、胃の中にガスが溜まりやすくなることもあります。
→ リラックス法や生活習慣の改善、必要に応じて整胃剤を使用します。
胃食道逆流症(GERD)
胃食道逆流症(GERD)は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流し、食道の粘膜に炎症を起こす病気です。
主な症状
- げっぷ
- 胸やけ
- 酸っぱい液が口に上がってくる(酸逆流)
- 胃もたれ・のどの違和感
これらの症状は食後や就寝時に悪化しやすいのが特徴です。
胃食道逆流症(GERD)とピロリ菌
ピロリ菌の除菌後は、一時的に胃酸分泌が増えてGERDの症状が出やすくなることがあります。
しかし、除菌治療自体は胃がんの予防に非常に重要であり、除菌が直接GERDを「悪化させる」とは限りません。
リスク因子
胃食道逆流症(GERD)は複数の要因が重なって発症します。
- 生活習慣:暴飲暴食、早食い、高脂肪食、アルコール、喫煙、コーヒーや炭酸飲料、食後すぐ横になる習慣
- 身体的要因:肥満、妊娠、加齢、姿勢異常(猫背など)
- 解剖学的要因:食道裂孔ヘルニア
- 薬剤:降圧薬(Ca拮抗薬)、抗コリン薬、テオフィリン、鎮静薬など
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
潰瘍によって胃酸分泌が乱れ、げっぷや胃もたれが出ることがあります。
原因はピロリ菌感染、ストレス、NSAIDs(鎮痛薬)、飲酒・喫煙などです。
ピロリ菌が関与している場合は、胃酸を抑える薬+抗菌薬を用いた1週間程度の除菌療法を行うことで再発および胃がん発生のリスクを抑えることができます。
胃がん
早期胃がんは無症状のことも多いですが、進行するとげっぷ・胸やけ・胃もたれ・吐き気・体重減少が起こります。
早期発見であれば内視鏡治療や低侵襲手術で根治が可能です。健康診断で異常を指摘された場合は、早めに胃カメラ検査を受けましょう。
→ 胃がんは早期ステージでの発見ほど予後が良好で、早期がんの5年生存率は90%以上です。当院では外科手術を必要としない段階での早期発見を重視しています。胃カメラ検査は、これまでに早期癌の内視鏡診断5,000例以上の豊富な経験を持つ院長が担当いたします。
機能性ディスペプシア
内視鏡検査では異常が見つからないのに、慢性的に胃もたれ・げっぷ・腹部不快感が続く状態です。ストレスや自律神経の乱れ、胃の動きの低下が関与します。
糖尿病に伴う胃の排出遅延
糖尿病で胃の神経が障害されると、胃の排出が遅れ、ガスが溜まりやすくなりげっぷが増えることがあります。
飲食習慣
ガムや飴を常用する、喫煙習慣があると空気を飲み込みやすく、げっぷが増えることがあります。
おならがよく出る原因は?
病気のサイン?
 おなら(放屁)は誰にでも起こる自然な生理現象です。
おなら(放屁)は誰にでも起こる自然な生理現象です。
食べ物や飲み物、生活習慣によって腸内環境は大きく変わり、おならの量やにおいにも影響します。
一過性の変化であれば飲食物の影響が考えられますが、症状が長引く場合や強いにおい・お腹の張りを伴う場合は疾患が隠れている可能性もあります。
糖質・食物繊維の過剰摂取
糖質や食物繊維は大腸で腸内細菌に分解される際、水素やメタンといったガスが発生します。
そのため摂りすぎるとおならが増えることがあります。
ただし、この場合のおならは比較的においが弱いのが特徴です。
タンパク質・にんにくなどの過剰摂取
タンパク質は腸内で悪玉菌(例:ウェルシュ菌)によって分解されると、硫化水素などのガスが発生し、腐った卵のような強いにおいになります。
にんにくなど硫黄を多く含む食品は「アリルメチルスルフィド類」と呼ばれる臭気成分となり、体内に長く残るため強いにおいのおならにつながります。
炭酸飲料の飲みすぎ
炭酸飲料やビールなどの発泡性飲料は、胃や腸にガスが蓄積しやすく、おならの回数が増える原因になります。
便秘で溜まる腸内ガス
便秘になると腸内で便が長く滞留し、発酵や腐敗が進んでガスが多く発生します。
このガスは強いにおいを伴うことが多く、腸内で発生した有害物質が血流を介して体に吸収され、倦怠感や肌荒れの原因になることもあります。
ストレスで増える腸内ガス・呑気症(どんきしょう)
緊張やストレスで無意識に空気を飲み込み(嚥下)、胃腸に空気が溜まるとおならやげっぷが増えます。
これを「呑気症」と呼びます。げっぷが増えることで逆流性食道炎のリスクも高まり、胸やけや胃の不快感につながることがあります。逆流性食道炎が疑われる場合には、正確な診断のために胃カメラ検査を受けることをおすすめします。
過敏性腸症候群(IBS)
腸の器質的異常は見られませんが、便秘や下痢、ガスの増加による腹部膨満感が続きます。
便秘型や混合型では便の滞留でガスが発生し、おならが増えることがあります。生活習慣の改善や薬物療法で改善が期待できます。
大腸がん
初期は症状が乏しいですが、進行すると腸の通過障害で便秘や細い便が出るようになり、ガスが溜まります。
おならは1日何回までが正常?
おならの回数には個人差がありますが、1日10回前後が一般的とされます。
実際には数回〜数十回まで幅があり、食生活や腸内環境、体調によって左右されます。
平均より多くても病気ではないこともありますが、
を伴う場合は、消化器の病気が隠れている可能性があります。
げっぷ・おならが
よく出る方は
大阪市鶴見区の当院へ
げっぷやおならは生理現象ですが、症状が続いたり強くなったりする場合には病気が隠れていることもあります。
当院では、日本消化器病学会専門医・指導医が丁寧に問診・検査を行い、必要に応じて胃カメラ・大腸カメラや血液検査などで原因を特定します。
原因に応じた治療で症状を改善し、生活の質(QOL)の向上を目指します。