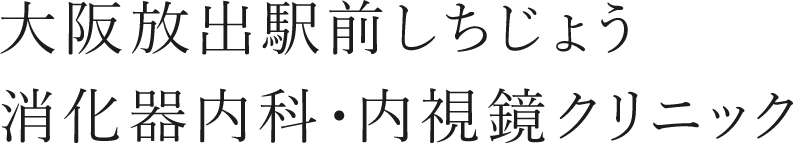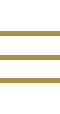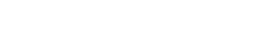慢性腎臓病(CKD)とは

腎臓は、腰の少し上・背中側に左右1つずつある臓器で、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体の外に出しています。1日におよそ200リットルもの血液をろ過していると言われる、とても大切な臓器です。
この腎臓の働きが何らかの原因で低下し、老廃物や水分がうまく排出できなくなると、体にむくみやだるさなどの症状が出てきます。このような状態が慢性的に続くことを「慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)」と呼びます。
原因は糖尿病や高血圧などの生活習慣病が多いですが、はっきりした理由が分からない場合もあります。放っておくと腎不全に進行し、透析治療が必要になる場合や、心臓・血管への影響で命に関わることもあります。
そのため、腎臓の働きをできるだけ長く保つための継続的な治療と管理がとても大切です。日本腎臓学会でも、原因にかかわらず腎機能を守ることを重視したガイドラインが設けられています。
慢性腎臓病(CKD)を判断する基準
次のような状態が3か月以上続くと、慢性腎臓病(CKD)と診断されます。
- 腎臓のろ過機能を示す「GFR(糸球体ろ過量)」が正常の60%未満に低下している
- 尿検査や血液検査、腹部エコー・CTなどで腎臓に異常がある
腎臓は、老廃物の排出や、水分・塩分のバランスを保つ重要な臓器です。その機能が低下すると、老廃物の蓄積・むくみ・高血圧・貧血などが起こることがあります。ただし、早い段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な検査で早めに異常を見つけることが大切です。
慢性腎臓病(CKD)を診断するための検査
腎臓の状態を調べる基本の検査は、尿検査と血液検査です。必要に応じて、腹部エコー(超音波検査)やCT検査を行うこともあります。
尿検査
尿に本来含まれない成分が混じっていないかを確認します。
タンパク尿
腎臓のろ過機能が低下すると、尿にタンパク質が漏れ出ます。ただし、健康な方でも激しい運動や発熱などで一時的に出ることもあります。
微量アルブミン尿
アルブミンという血液中のタンパク質の一種で、糖尿病の初期段階で現れやすく、糖尿病性腎症の早期発見に役立ちます。
潜血反応
尿に血液が混じっている状態です。目で見えないほど微量な場合もあり、腎臓や尿路系に異常があるサインです。
尿糖
通常、血液中の糖は腎臓で再吸収されるため尿に出ません。しかし血糖値が高いと再吸収が追いつかず、尿に糖が混じるようになります。一時的な要因で増えることもあるため、血液検査とあわせて判断します。
血液検査
腎臓は老廃物を尿に排出するほか、赤血球を作るホルモン(エリスロポエチン)を分泌するなど血液と深く関わっています。そのため血液検査によって腎機能を評価します。
クレアチニン
筋肉から出る老廃物で、腎臓が正常に働いていればほぼ全てろ過されます。数値が高いと腎機能低下を示します。eGFR(推定糸球体ろ過量)の計算にも使われます。
血清尿素窒素(BUN)
タンパク質の代謝でできる老廃物です。腎機能が落ちると血中で増加します。ただし肝臓などの異常でも変動するため、クレアチニンとあわせて評価します。
その他の項目
腎機能が悪化すると、血中のカリウムが上がり「高カリウム血症」になることがあります。そのほか、ナトリウム・カルシウム・クロールなどのバランスも重要です。また、腎臓で作られるホルモン(エリスロポエチン)が減ると、ヘモグロビンやヘマトクリットの値が低下し、貧血になることもあります。
慢性腎臓病(CKD)の段階ごとの治療方針
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の働きの程度(eGFR値)によってステージ(段階)が分けられています。それぞれの段階に応じて治療や管理を行っていきます。
|
ステージ |
重症度の目安 |
eGFR(mL/min/1.73㎡) |
治療の考え方 |
|---|---|---|---|
|
G1 |
ハイリスク群(GFRは正常または高値で、腎臓に負担をかける要因がある場合) |
≧90 |
高血圧・糖尿病など、CKDにつながる疾患の治療を行い、リスクを減らします。 |
|
G2 |
腎臓に軽い障害があり、GFRは正常または軽度低下 |
60~89 |
原因となる疾患の治療に加え、腎機能の悪化を防ぐための生活改善や薬物療法を行います。 |
|
G3a |
腎臓に障害があり、GFRが軽度~中等度低下 |
45~59 |
ステージG2の治療を続けつつ、腎機能の進行度に応じた対応を強化します。 |
|
G3b |
GFRが中等度~高度低下(腎機能が半分程度) |
30~44 |
ステージG3aの治療に加えて、糖尿病や高血圧など合併症の治療をしっかり行い、腎臓への負担を減らします。 |
|
G4 |
GFRの高度低下 |
15~29 |
ステージG3bの治療を継続しながら、将来的な腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植など)の準備を始めます。 |
|
G5 |
末期腎不全(ESRD:End-Stage Renal Disease) |
<15 |
尿毒症などのリスクが高く、腎代替療法による治療を開始します。 |
慢性腎臓病(CKD)の治療について

慢性腎臓病(CKD)には、
- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病によるもの
- 明確な原因がわからないまま腎機能が低下していくもの
があります。原因となる病気が分かっている場合は、まずその治療を優先することで腎臓の働きが改善することがあります。高血圧や糖尿病のほか、自己免疫疾患などが原因となることもあり、それぞれの疾患に応じた薬物療法を行います。
食事療法の重要性
腎臓を守るためには、薬だけでなく食事の工夫もとても大切です。塩分(ナトリウム)やカリウム、たんぱく質を摂りすぎると腎臓に負担がかかります。特に腎機能が低下すると、体の中にカリウムが溜まりやすくなり、病状をさらに悪化させることがあります。そのため、栄養バランスを保ちながら、無理のない食事を続けることが大切です。
当院では、患者様が無理なく、かつ美味しく食事を続けられるよう、献立や食べ方についてもアドバイスを行っています。食事や栄養面でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。