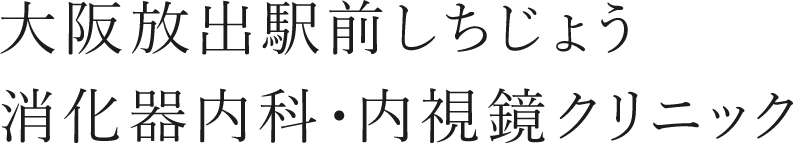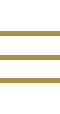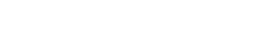お腹の張り・腹部膨満感
 腹部膨満感とは、お腹が張ったように感じる状態や、ガスが溜まっているような不快感を指します。多くの場合、
腹部膨満感とは、お腹が張ったように感じる状態や、ガスが溜まっているような不快感を指します。多くの場合、
- 食べ過ぎや早食い
- 食物繊維の不足
- 過度なダイエット
- 運動不足
- 便秘
といった生活習慣が原因で消化管内にガスがたまり、膨満感が起こります。
しかし、膨満感は単なる食生活や生活習慣によるものだけではなく、何らかの病気が原因となっている場合もあります。例えば、胃腸の疾患や肝臓・腎臓の病気によって腹水(お腹に液体がたまる状態)が生じると、同じようにお腹の張りを感じることがあります。
受診をおすすめする症状
次のような症状を伴う場合は、早めの受診を強くおすすめします。
- 息苦しさや強い腹痛がある
- 食べ過ぎなど明らかな原因がないのに急にお腹が張った
- 少し食べただけで満腹になる(早期膨満感)
- 夜間・就寝中も膨満感が続く
- むくみや尿量の減少がある
- げっぷが多い
- 慢性的な便秘がある
腹部膨満感は多くの方が経験する身近な症状ですが、背景に重大な病気が隠れていることもあります。気になる症状が続く場合は、自己判断せずに早めにご相談ください。
お腹が張る原因
便秘・腸のガス溜り
便秘は、腹部膨満感(お腹の張り)の代表的な原因のひとつです。腸の動きが低下してガスや便が腸内に滞留することで、お腹の張りや不快感が生じます。
便秘の定義
便秘とは、本来排泄されるべき便が大腸内に滞ることで起こる症状を指し、具体的には以下のような状態を含みます。
- コロコロとした兎糞状便や硬い便
- 排便回数の減少
- 強くいきまないと排便できない
- 排便後もすっきりしない(残便感)
- 直腸や肛門に詰まった感じ(閉塞感)
- 排便そのものが困難
慢性便秘症
「慢性便秘症」とは、便秘が長期間続き、日常生活に支障をきたす病態をいいます。日本ではおよそ10〜15%の方が慢性便秘症に悩まされているとされています。
発症のリスク要因としては以下が知られています。
- 女性であること
- 身体活動量の低下
- 過去の腹部手術歴
- 精神疾患や神経疾患などの基礎疾患
- 加齢
- 一部の薬剤の影響
便秘薬の注意点
便秘薬にはさまざまな種類があります。
一時的な便秘であれば、市販薬で改善する場合もあります。
しかし、市販薬の中には長期間使うことで腸の機能がかえって低下し、便秘が悪化する可能性があるもの(刺激性下剤など)もあります。
そのため、便秘が慢性的に続く、または市販薬でなかなか効果が得られない場合には、自己判断で薬を続けず、一度医師にご相談いただくことが大切です。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群(IBS)は、お腹の不快感や痛みに加えて、便秘(便秘型)や下痢(下痢型)などの便通のトラブルが続く病気で、日本人の約10人に一人が悩まれています。ストレスや腸内細菌のバランスの乱れなどが原因になります。命に関わることはありませんが、「電車やバスでトイレに行けないのが不安」「仕事中もお腹の調子が気になって集中できない」といったように、生活の質(QOL)を大きく下げてしまいますので、お心当たりの方はお早めに当院までご相談ください。
腸閉塞(イレウス)
腸閉塞(イレウス)とは、腸の一部が狭くなったり塞がったり、動きが麻痺することで、食べ物のカスやガス、便が腸の先に進めなくなった状態をいいます。
主な症状
腸閉塞が起こると、次のような症状が見られることがあります。
- おならや排便が出なくなる
- 吐き気や嘔吐
- 強い腹痛や張り
- 食欲不振
これらの症状は放置すると悪化し、腸の血流障害や穿孔(穴があくこと)につながる危険性もあります。
診断方法
腸閉塞は、腹部レントゲンや超音波(エコー)、必要に応じてCT検査などで診断します。
治療
- 軽度の場合は 絶食や点滴などで腸を安静にし、自然に回復することもあります。
- しかし、腸が完全に塞がっている場合や血流障害が疑われる場合は、緊急手術が必要になることもあります。
腸閉塞は誰にでも起こり得る病気であり、早期の発見・治療が非常に大切です。
「おならや便が出ない」「強いお腹の張りや痛みがある」といった症状が続く場合には、自己判断せずに早めに医療機関を受診してください。
呑気症(どんきしょう)
呑気症(どんきしょう、別名:空気嚥下症)とは、無意識に空気を飲み込み、その空気が胃や腸にたまってしまうことで、お腹の張り(膨満感)やげっぷなどが起こる状態をいいます。
主な症状
- おならやげっぷが増える
- お腹の張り(腹部膨満感)
- 胸やけ、不快感
- 時に胃の痛みや食欲不振
これらの症状は命に関わるものではありませんが、日常生活の質を下げる大きな原因になります。
呑気症の原因
私たちは食事や会話の際に自然と空気を吸い込んでいますが、次のような場合は特に空気を飲み込みやすくなります。
- 一度に大量に口へ入れて食べる
- 早食い、よく噛まないで飲み込む習慣がある
- 炭酸飲料やガム、飴をよく口にする
- 緊張やストレスが強い
- 口呼吸になりやすい
こうした習慣や要因により、知らないうちに多くの空気を取り込み、症状へつながることがあります。
対策と治療
- 食事はよく噛み、ゆっくり食べる
- 炭酸飲料やガム・飴を控える
- 鼻呼吸を意識する
- ストレスを和らげる生活習慣を取り入れる
症状が続く場合は、胃カメラや腹部検査で他の病気が隠れていないかを確認する。
呑気症は生活習慣やストレスと関わりが深い症状ですが、逆流性食道炎や胃腸の病気と似た症状を示すこともあるため、自己判断せずに医療機関での診察をおすすめします。
機能性ディスペプシア
症状の原因となる潰瘍・がんなどの器質的疾患、全身性疾患、代謝性疾患がないにもかかわらず、慢性的に心窩部痛(みぞおちの痛み)や胃もたれなど、心窩部を中心とした腹部症状を示す病気です。
上腹部症状で受診される患者さんのおよそ半数が機能性ディスペプシアとされ、具体的な症状には、腹痛、不快感、胃痛、食後の胃もたれ、早期飽満感(少量でお腹がいっぱいになる)、早期満腹感、腹部膨満感、胃内停滞感(食べ物がいつまでも残っている感じ)、食欲不振、悪心、嘔吐などがあります。
これまで、このような症状があっても胃カメラで異常が見つからない場合、「慢性胃炎」と診断され治療されることが多くありました。
しかし近年では、発症には胃の運動異常や知覚過敏、胃酸分泌の変化、ストレスや生活習慣など、複数の要因が複合的に関与していると考えられるようになっています。
胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの器質的疾患が症状の原因であることがあるため、機能性ディスペプシアの確定診断には器質的疾患の除外が必要です。
症状に応じて、血液検査、胃カメラ検査、腹部超音波検査などを組み合わせ、上部消化管の器質的異常の有無を確認します。
がん
腹部膨満感は、生活習慣や便秘だけでなく、胃がん・大腸がん・卵巣がん・膵臓がんなどの腹部のがんによって起こることもあります。これらの病気では、胃や腸の機能が低下したり、腸の通過が妨げられることで膨満感が生じることがあります。
また、腹部で炎症が起こり、腹水(お腹に水がたまる状態)が蓄積する場合も膨満感の原因になります。
診断方法
腹部の状態を詳しく調べるためには、以下の検査が有用です。
- 腹部超音波検査(エコー):お腹の臓器や腹水の有無を確認
- 胃カメラ(上部消化管内視鏡):胃や食道の状態を詳しく観察
- 大腸カメラ(下部消化管内視鏡):大腸や直腸の状態を確認
治療について
患者さまの状態や原因に応じて、
- 利尿剤(腹水の改善を目的)
- 胃腸の働きを整える薬(消化管の運動を促進)
などのお薬を使用する場合があります。
腹部膨満感は、単なる生活習慣によるものだけでなく、重大な病気のサインである可能性もあります。症状が長く続く、急に強くなったといった場合には、早めの受診と検査をおすすめします。
便秘について
便秘の原因と検査
便秘は一時的に起こることもありますが、慢性的に続く場合にはいくつかのタイプに分けられます。原因を正しく把握することが、適切な治療につながります。
便秘の主な原因分類
① 機能性便秘(一次性便秘)
腸や肛門に明らかな病気がなく、腸の動きや排便の機能の異常で起こる便秘です。
- 機能性便排出障害:直腸や肛門の感覚や動きが弱くなり、残便感や排便困難を生じるタイプ
- 大腸通過正常型:便はある程度動いているが、排便がスムーズにいかないタイプ
- 大腸通過遅延型:腸全体の動きが遅く、便が長くとどまってしまうタイプ
② 非狭窄性器質性便秘(一次性便秘)
腸そのものの形態や運動に異常がある場合です。
- 小腸・結腸障害型:巨大結腸、慢性偽性腸閉塞など
- 直腸・肛門障害型:直腸瘤、直腸重積、肛門アカラシアなど
③ 二次性便秘
他の病気や薬が原因で起こる便秘です。
- 薬剤性便秘:抗コリン薬、抗うつ薬、抗精神病薬、オピオイド(強い痛み止め)などによって起こる
- 症候性便秘:糖尿病、甲状腺機能低下症、パーキンソン病、強皮症などの病気に伴って起こる
- 狭窄性便秘:大腸がんやクローン病などにより、腸が狭くなって便が通れなくなる
便秘の症状による分類
- 排便回数減少型:便が出る回数が少ない
- 排便困難型:便はあるのに出しにくい
便秘の背景に関与する要因
- 結腸の運動低下、感覚の変化
- 直腸や肛門の排便機能障害
- 便意の消失
- 不安やうつなどの心理的要因
- 腸内細菌バランスの乱れ
便秘の診察と検査
診察
- 腹部診察:お腹の張りや腸の動きを確認
- 直腸肛門診:排便困難がある場合に直腸や肛門の状態を確認
検査
- 血液検査:糖尿病・甲状腺機能・貧血・カルシウム異常などを調べます
- 直腸エコー・腹部エコー:便やガスの停滞、臓器の異常の有無を確認
- 大腸カメラ:大腸がんや炎症性腸疾患などを調べます
- 腹部レントゲン:腸閉塞や腸のねじれ(結腸軸捻転)、ガスの分布を確認
注意すべき「警告症状」
次のような症状がある場合は、重大な病気が隠れている可能性があるため、早めの受診が必要です。
- 急に排便習慣が変わった
- 血便が出る
- 半年以内に3kg以上の体重減少がある
- 発熱や関節痛がある
- お腹にしこりや腫れを感じる
- 直腸診で腫瘤や血液が確認される
- 50歳以上で初めて便秘が強くなった
- 大腸の病気の既往や家族歴がある
便秘は単なる生活習慣の問題だけでなく、大腸がんや全身疾患のサインであることもあります。市販薬で改善しない、症状が長引く、警告症状がある場合には、放置せずに医師の診察を受けることが大切です。
便秘の治療
慢性便秘症の治療の目標は、自然な排便が無理なくできる状態に導き、その状態を維持すること、そして日常生活の質(QOL)を改善することです。
生活習慣と食事の工夫
便秘の改善には、薬だけでなく生活習慣や食事を整えることが大切です。
- 食物繊維の摂取
- 水溶性食物繊維(グアーガム分解物〈PHGG〉など)は排便回数を増やし、便秘薬の使用を減らす効果が報告されています。
- キウイ、プルーン、オオバコ(サイリウム)は自然な排便回数の増加に役立ちます。
- 発酵性食物繊維の効果
腸内で発酵されると「酪酸」という物質が作られ、腸の動きを促すセロトニンの分泌を高めます。 - 適度な運動
身体活動量が多い方では、食物繊維の効果で便がやわらかくなりやすくなります。 - 腹部マッサージ
1日15分、週5回程度のお腹のマッサージは、便秘症状の改善に有効とされています。 - プロバイオティクス(善玉菌)
一部の乳酸菌(Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum など)は排便回数を増やし、腹部の不快感を軽減する効果が示されています。
慢性便秘症と全身の健康
慢性便秘症は単なる腸の不調にとどまらず、研究によって以下の関連が報告されています。
- 心血管疾患(心筋梗塞・脳梗塞など)の発症リスク上昇
- パーキンソン病や腎疾患の発症リスク上昇
- 大腸がんとの直接的な関連は明らかになっていません
そのため、便秘は「よくある症状」と軽視せず、全身の健康を守るためにも改善していくことが大切です。
慢性便秘症は生活習慣の見直しと、必要に応じた薬物療法を組み合わせることで改善が期待できます。
「薬に頼らずに改善できる部分」も多いため、ぜひ日常生活の中で取り入れてみてください。症状が続く場合には、一度ご相談ください
便秘薬の種類
便秘薬にはさまざまな種類があり、体質や便秘のタイプによって合う薬・合わない薬があります。自己判断で使い続けると逆に便秘が悪化することもあるため、医師と相談しながら適切に選ぶことが大切です。
主な便秘薬の種類
- 膨張性下剤(カルボキシメチルセルロース、ポリカルボフィルカルシウム)
水分を吸って便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促します。 - 浸透圧性下剤
腸に水分を引き込み、便をやわらかくする薬です。
- 塩類下剤:酸化マグネシウムなど
- 糖類下剤:ラクツロース、マンニトール、ソルビトールなど
- 高分子化合物:ポリエチレングリコール(腸内の水分量を調整しながら自然な排便を促す)
- 浸潤性下剤:便の表面張力を下げてやわらかくする
- 刺激性下剤(センナ、センノシド、ダイオウ、ビサコジル、ピコスルファートナトリウムなど)
大腸の神経や筋肉を直接刺激して排便を促します。効果は強いですが、耐性や習慣性を避けるため短期間・必要最小限の使用が原則です。 - 粘膜上皮機能変容薬(ルビプロストン、リナクロチド)
腸の粘膜から水分を分泌させ、便をやわらかくして排便を助けます。近年の新しい便秘治療薬です。 - 胆汁酸トランスポーター阻害薬(エロビキシバット)
胆汁酸の再吸収を抑えることで、腸管内に水分を増やし、蠕動運動を促進します。 - 消化管運動機能改善薬(モサプリドなど)
腸の動きを改善しますが、慢性便秘症には保険適応がありません。 - 漢方薬(大建中湯など)
体質や症状に合わせて使用し、お腹の張りや冷えを伴う便秘に用いられることがあります。
便秘やお腹の張りでお困りの方は大阪市鶴見区の当院へ
便秘や腹部膨満感の原因は、生活習慣や体質だけでなく、過敏性腸症候群や大腸がんなどの病気によっても起こることがあります。そのため、症状が長く続く場合には原因をしっかり調べることが大切です。
当院では、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、大腸肛門病専門医、日本消化管学会認定「便通マネージメントドクター」である院長のもと診察から検査・治療まで包括的に対応いたします。必要に応じて、採血・腹部超音波(エコー)・大腸カメラ検査も行い、患者さま一人ひとりに合った治療を提案します。
「市販薬を使っても改善しない」「便秘薬を長く飲み続けて不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。