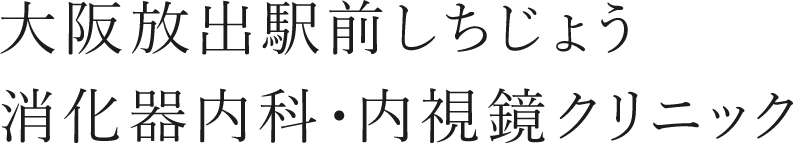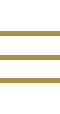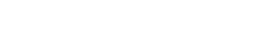下痢とは
 下痢とは、「便の形状が軟便あるいは水様便となり、かつ排便回数が増加する状態」と定義されます。正常な排便回数の目安は1日2〜3回から週3回程度ですが、排便の頻度は食習慣や生活環境により大きく異なり、個人差があります。
下痢とは、「便の形状が軟便あるいは水様便となり、かつ排便回数が増加する状態」と定義されます。正常な排便回数の目安は1日2〜3回から週3回程度ですが、排便の頻度は食習慣や生活環境により大きく異なり、個人差があります。
私たちが口から摂取した食べ物は、食道・胃・小腸・大腸といった消化管を通過する中で消化・吸収され、最終的に便として肛門から排出されます。この過程で、大腸では水分の吸収が行われますが、その吸収が不十分であったり、腸内に過剰な水分が存在したりすると、便は軟らかくなり、下痢になります。
下痢が長期間続くと、脱水や電解質異常、さらには低栄養状態といった合併症を引き起こす可能性があります。こうした状態を予防するためにも、下痢が続く場合は早めの対応が重要です。
下痢について
形
理想的な便の形状は、表面が滑らかで柔らかいソーセージ状とされています。これに対し、柔らかく形があいまいな不定形の便は「軟便傾向」と考えられ、それよりもさらに水分が多く形状を保てないような便は「下痢傾向」にあるとされます。一方で、逆に硬さが目立つ便は「便秘傾向」にある可能性があります。

ブリストルスケール
水分量
便の硬さは、含まれる水分量によって大きく左右されます。通常の便の水分量はおよそ70〜80%とされていますが、水分量が80〜90%に達すると軟便となり、90%を超えると水様便、すなわち下痢になります。
期間による分類
下痢はその持続期間によって「急性下痢」と「慢性下痢」に分類されます。急性下痢の代表的な原因は腸管感染症で、通常は1週間以内、長くても4週間以内に自然軽快することが一般的です。
一方で、慢性下痢症は「4週間以上持続または反復する下痢のために日常生活に様々な支障をきたした病態」と定義されます。頻繁な排便、急な便意(便意切迫感)、便失禁、腹痛などの症状がみられ、学業や就労、睡眠といった生活全般に影響を与えるため、検査や生活指導、薬物療法などが必要な状態です。
下痢は出し切った方がいい?
感染性の下痢が疑われる場合は、むやみに下痢止めを使用して症状を抑えようとするのではなく、原因となるウイルスや細菌を体外に排出することが大切です。そのため、基本的には下痢止めの使用は控えることが推奨されます。
症状がある間は、脱水を防ぐためにこまめな水分補給を心がけ、お腹を冷やさず、できるだけ安静に過ごしてください。
また、下痢によって仕事や睡眠など日常生活に支障をきたしている場合には、早めに医療機関を受診し、必要な検査を受けて原因を特定した上で、適切な治療を受けることが大切です。
下痢を起こす原因
食べ物や飲み物
脂っこい食品(揚げ物やバター、クリームなど)や、刺激の強い食品(唐辛子や香辛料)、冷たい飲食物(アイスクリームや冷たいジュースなど)、人工甘味料を多く含む食品、アルコール、カフェインを含む飲み物(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)は、腸を刺激して下痢の原因になることがあります。
また、乳糖不耐症の方では、牛乳やヨーグルトなどの乳製品を摂りすぎることで下痢を引き起こすことがあるため、注意が必要です。
これらの食品や飲み物は、体調がすぐれない時や下痢が続いている時には控えるようにしましょう。
ウイルスや細菌
飲食物に含まれる細菌やウイルスが原因で食中毒(感染性腸炎)を起こすと、重度の下痢や嘔吐、発熱といった症状がみられることがあります。
主な原因として知られている病原体には、ロタウイルスやノロウイルスといったウイルスのほか、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌(O-157など)などの細菌があります。
これらの病原体は、加熱不十分な食品や汚染された水・食材などを介して体内に侵入し、腸管に炎症を引き起こします。感染予防のためには、食品の十分な加熱・手洗いの徹底・調理器具の衛生管理が重要です。
薬
お薬の服用が原因で、下痢が起こることがあります。特に抗生物質は、腸内の善玉菌を減らすなど腸内環境に影響を与え、下痢を引き起こすことがあります。
また、抗がん剤や免疫抑制剤、胃薬(制酸薬など)も、腸への刺激や消化機能の変化を通じて、下痢の原因となることがあります。
こうした薬剤による下痢は、服用を中止または変更することで改善することもありますので、下痢が続く場合やつらい症状がある場合は、自己判断で薬を中止せず、必ず医師や薬剤師にご相談ください。
胃腸の病気
胃腸の疾患があっても、「自分は元気だから大丈夫」と思い込み、症状に気づかないことがあります。
例えば過敏性腸症候群(IBS)では、食事やストレスなどの影響で腸が過敏に反応し、下痢や腹痛、便秘などの症状が現れることがあります。
一見、健康に見えても腸内では異常が起きている場合があるため、気になる症状が続くときは早めの受診が大切です。
過敏性腸症候群
腸に器質的な異常がないにもかかわらず、便秘や下痢などの症状が繰り返し起こる病気です。有病率は約10%とされ、比較的よくみられる疾患です。原因としては、感染性腸炎の既往やストレス、腸内細菌のバランスの乱れ、腸の粘膜の軽微な炎症などが関与していると考えられています。
症状の現れ方によって、以下の4つのタイプに分類されます。
- 便秘型
- 下痢型
- 混合型(便秘と下痢を交互に繰り返す)
- 分類不能型(上記に当てはまらないもの)
日常生活に支障をきたすことも多いため、症状が続く場合は早めの診察をおすすめします。
潰瘍性大腸炎
直腸から大腸にかけて炎症が広がり、血便・下痢・腹痛などの症状を引き起こす慢性の腸疾患です。近年は発症数が増加傾向にあり、日本では約500人に1人が罹患しているとされ、厚生労働省の指定難病にも認定されています。病状は、症状が強く現れる「活動期」と、症状が落ち着く「寛解期」に分けられます。
進行した大腸がん・大きな大腸ポリープ
大腸ポリープや大腸がんの初期段階では、自覚症状がほとんどありません。進行した大腸がんや大きな大腸ポリープでは、腸管が狭くなり、便が通過する際に病変と擦れて出血や血便がみられることがあります。ただし、初期の大腸がんやポリープはほとんど自覚症状がなく、気づかないまま進行してしまうことも少なくありません。
そのため、定期的な内視鏡検査による早期発見・早期治療が非常に重要です。
下痢の種類
下痢は、症状の持続期間や原因に応じて以下のようにいくつかのタイプに分類されます。
症状の持続期間による分類
症状の持続期間に応じて、「急性下痢」と「慢性下痢」に分類されます。
急性下痢
数時間から2週間以内に自然に軽快することが多い下痢です。
主な原因としては、ウイルスや細菌による腸管感染症、ストレス、食べ過ぎ・飲み過ぎ、不適切な食事などが挙げられます。
特に多いのが腸管感染症によるもので、通常は1週間以内、多くても4週間以内に改善します。
予防には、規則正しい食生活や衛生管理が重要です。
慢性下痢
「4週間以上にわたって持続または繰り返す下痢のために日常生活に様々な支障をきたした病態」のことです。頻回の排便、便意切迫感、便失禁、腹痛などの症状がみられ、日常生活(学業・仕事・睡眠など)に支障をきたし、原因精査のための検査や、食事・生活指導、薬物療法などが必要になることもあります。
原因による分類(慢性下痢症)
下痢は、原因に応じて大きく8つのタイプに分けられます。
薬剤性下痢症
薬の影響で腸が刺激されて下痢が起こることがあります。
特に、抗生物質や下剤、胃薬、抗がん剤などでよく見られます。薬を変えたり中止したりすることで治ることもあります。
食物起因性下痢症
脂っこいもの、冷たいもの、アルコール、牛乳(乳糖不耐症)などが原因で下痢になることがあります。食生活の見直しが大切です。
症候性(全身疾患性)下痢症
甲状腺の病気や糖尿病、膵臓の病気など、体の他の部分の病気が関係して下痢になることがあります。この場合は、まず元の病気の治療が必要です。
感染性下痢症
ウイルス(ノロ・ロタ)や細菌(サルモネラ・カンピロバクターなど)が腸に感染して起こる急な下痢です。発熱や腹痛を伴うこともあり、人にうつることもあります。
器質性下痢症(炎症性や腫瘍性)
潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸がんなど、腸に実際の異常や炎症がある場合に起こる下痢です。血便や体重減少を伴うこともあり、大腸カメラなどの検査が必要になることがあります。
胆汁酸性下痢症
食べ物の消化に使われる胆汁が腸に流れすぎると、下痢になることがあります。胆のうを手術で取ったあとや、腸の一部を切除した人に起こることがあります。
機能性下痢症
検査をしても異常は見つからないけれど、繰り返し水っぽい便が出る状態です。体質や生活習慣、ストレスなどが関係していると考えられています。
下痢型過敏性腸症候群症(下痢型IBS)
ストレスや不安で腸が過敏になり、急な下痢や腹痛が起こることがあります。排便すると少し楽になるのが特徴です。生活習慣の見直しやお薬による治療で改善が期待できます。
下痢になったときの対処法
下痢が起こった場合、その原因や種類によって適切な対処法は異なります。
特に、重度の下痢や血便、吐き気、発熱などの症状がある場合は、ご自身で判断せず、当院までご相談ください。
症状や経過を詳しくお伺いしたうえで、必要に応じて以下のような検査を行い、原因に迫り治療法をご提案します。
- 採血検査(院内に採血機器を備えており、その場で迅速に結果をご説明できます)
- 便の検査
- 腹部超音波検査(当日、その場で検査が可能です。腸の状態や他の臓器との関連も確認します)
- 大腸内視鏡検査 (大腸の粘膜を直接観察し、ポリープや炎症、がんの有無を詳しく評価します。)
次に軽症の場合の一般的な対処法を解説します。
急性下痢の場合
下痢が続くと、脱水症状を起こすことがあります。
そのため、まずはこまめな水分補給が大切です。
冷たい飲み物は腸を刺激することがあるため、薄めの番茶・麦茶・湯冷まし・常温のミネラルウォーター、スポーツドリンクなどを、少量ずつ何回かに分けて飲むようにしましょう。
また、食事は胃腸に負担をかけないように、消化の良いものを選びましょう。
おすすめの食品は以下のとおりです。
- すりおろしリンゴ
- おかゆ
- 卵料理(半熟卵や茶碗蒸しなど)
- 脂肪の少ない白身魚や鶏ささみ
- 野菜をやわらかく煮込んだスープ
一方で、脂っこい料理や辛いもの、冷たい飲み物は控えるようにしてください。
また、無理な外出や仕事は避けて、十分に体を休めることも大切です。
しっかりと休養をとり、腸をいたわる生活を心がけましょう。
慢性下痢の場合
慢性的な下痢が続く場合は、ほかの病気が関係している可能性もあるため、早めに専門医の診察を受けることをおすすめします。
また、牛乳や特定の食品を摂取したときに下痢が起こる場合は、その食品が体に合っていない可能性があるため、しばらく控えるようにしましょう。
食事は、胃腸への負担を軽減しながら、栄養バランスにも配慮することが大切です。
おすすめの食材は以下のとおりです。
- うどん、やわらかいごはん
- じゃがいも、さといもなど、よく煮た根菜類
- 白身魚、鶏のささみなど脂肪の少ないたんぱく質
- 納豆、豆腐などの大豆製品
- リンゴ(すりおろしでも可)、バナナなどの果物
刺激の強い食べ物や脂っこい料理、冷たい飲み物は避け、ゆっくりよく噛んで食べることも意識しましょう。
市販薬の使用には注意
下痢止め(止瀉薬(ししゃやく)は一時的に症状を和らげる効果がありますが、使い方には注意が必要です。
特に、食中毒など感染性の下痢の場合、病原体を体外に排出することが重要です。むやみに下痢を止めると、症状が悪化したり、回復が遅れたりすることがあります。
一方で、腸内環境を整える「整腸薬」は、安全性が高く、下痢の改善に役立つことがあります。
乳酸菌、酪酸菌、ビフィズス菌を含む整腸薬は、腸内の善玉菌を増やし、腸内バランスを整える働きがあります。
また、体質や症状に応じては、漢方薬が有効な場合もあります。
ご自身で判断が難しい場合は、市販薬を使う前に一度ご相談ください。
症状や原因に合わせた適切な治療をおすすめします。
下痢が続く方は
大阪市鶴見区の当院へ
 下痢は何らかの病気や体の不調が原因となって起こっていることがあります。
下痢は何らかの病気や体の不調が原因となって起こっていることがあります。
原因を特定せずに放っておくと、症状が長引いたり、生活に支障をきたすことも少なくありません。
しかし、適切な診断と治療によって下痢が改善すれば、生活の質(QOL)を大きく向上させることができます。
当院では、患者様の症状や背景をお伺いし、必要に応じた検査を行ったうえで、適切な治療法をご提案いたします。
下痢が続いている方、繰り返す下痢にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。