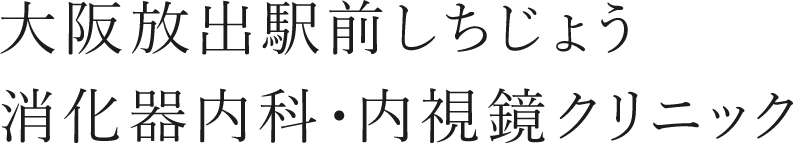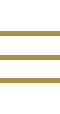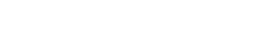- 機能性ディスペプシア
- 機能性ディスペプシアの原因は
ストレス? - 機能性ディスペプシアの症状
- 機能性ディスペプシアの検査・診断
- 機能性ディスペプシアの治療・お薬
- 機能性ディスペプシアを放置すると
どうなる?
機能性ディスペプシア
 英語の Functional Dyspepsia(FD) は、日本語で「機能性ディスペプシア」と訳されます。
英語の Functional Dyspepsia(FD) は、日本語で「機能性ディスペプシア」と訳されます。
これは、症状の原因となる潰瘍・がんなどの器質的疾患、全身性疾患、代謝性疾患がないにもかかわらず、慢性的に心窩部痛(みぞおちの痛み)や胃もたれなど、心窩部を中心とした腹部症状を示す病気です。
上腹部症状で受診される患者さんのおよそ半数が機能性ディスペプシアとされ、具体的な症状には、腹痛、不快感、胃痛、食後の胃もたれ、早期飽満感(少量でお腹がいっぱいになる)、早期満腹感、腹部膨満感、胃内停滞感(食べ物がいつまでも残っている感じ)、食欲不振、悪心、嘔吐などがあります。
これまで、このような症状があっても胃カメラで異常が見つからない場合、「慢性胃炎」と診断され治療されることが多くありました。
しかし近年では、発症には胃の運動異常や知覚過敏、胃酸分泌の変化、ストレスや生活習慣など、複数の要因が複合的に関与していると考えられるようになっています。
機能性ディスペプシアの原因はストレス?
機能性ディスペプシアは、生活上のストレスをはじめ、食生活の乱れ、睡眠不足、過労など、さまざまな要因との関連が指摘されています。
主な原因
近年では、下記に挙げる複数の要因が互いに影響し合い、発症や症状の持続に関与していると考えられています。
-
胃・十二指腸運動能異常
-
内蔵知覚過敏
-
心理社会的因子(生活上のストレス、性格、心理状態、対処能力、社会的支援)
-
胃酸分泌
-
遺伝
-
生育環境
-
感染性胃腸炎
-
運動・睡眠・食事内容や食習慣などのライフスタイル
過労、不規則な生活や睡眠不足、早食い、香辛料や脂質が多い食事 -
ピロリ菌感染(H. pylori関連ディスペプシア)
機能性ディスペプシアの症状
次のいずれかの症状が1つでもある場合、機能性ディスペプシア(FD)の可能性があります。
- みぞおち付近(心窩部)の痛みや不快感
- 食事を始めてすぐに満腹になり、最後まで食べられない(早期飽満感)
- 食後の胃もたれ
- 食欲不振
- 吐き気(悪心)
- 嘔吐
これらの症状があり、医療機関での検査(胃カメラなど)で胃や十二指腸に器質的な異常が見つからなかった場合、機能性ディスペプシアの可能性が高まります。
機能性ディスペプシアの検査・診断
機能性ディスペプシアの診断には、胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)が推奨されます。特に、
- 高齢で新たに症状が出現した場合
- 体重減少
- 嘔吐を繰り返す
- 消化管出血(吐血・黒色便など)
- 嚥下障害・嚥下痛
- 腹部腫瘤
- 発熱
- 食道がん・胃がんの家族歴
といった症状や背景がある場合は、胃カメラ検査が強く勧められます。
これらに当てはまらない場合でも、胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの器質的疾患が症状の原因であることがあるため、FDの確定診断には器質的疾患の除外が必要です。
なお、感染性胃腸炎など胃カメラで診断できない疾患が原因のこともあるため、問診・診察で検査の優先順位を判断します。症状に応じて、血液検査、胃カメラ検査、腹部超音波検査などを組み合わせ、上部消化管の器質的異常の有無を確認します。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)
 胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)では、食道・胃・十二指腸の粘膜をリアルタイムで観察し、炎症・潰瘍・がんなどの病変の有無を確認します。必要に応じて、疑わしい部分の組織を採取し、病理検査を行うことで確定診断につなげます。
胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)では、食道・胃・十二指腸の粘膜をリアルタイムで観察し、炎症・潰瘍・がんなどの病変の有無を確認します。必要に応じて、疑わしい部分の組織を採取し、病理検査を行うことで確定診断につなげます。
当院では、内視鏡検査の経験が豊富な専門医がすべての胃カメラ検査を担当しています。最新の細径内視鏡を使用し、ご希望の方には鎮静剤を併用して、リラックスした状態で検査を受けていただけます。苦痛を最小限に抑え、安心して検査を受けていただくために、大阪大学麻酔科 名誉教授・藤野裕士先生のご監修のもと、安全性に十分配慮した鎮静(静脈麻酔)を行っております。また、経鼻内視鏡検査にも対応しており、吐き気が少なく快適に受けられるよう配慮しています。
腹部エコー(超音波)検査
 胃カメラ検査ではでは観察が難しい肝臓・膵臓・胆のうなどの病気が、症状の原因となっている場合があります。そのため、腹部超音波検査(腹部エコー)を併用し、これらの臓器の形態や状態を確認します。腹部超音波検査は体への負担が少なく、痛みや被ばくの心配もない安全な検査です。
胃カメラ検査ではでは観察が難しい肝臓・膵臓・胆のうなどの病気が、症状の原因となっている場合があります。そのため、腹部超音波検査(腹部エコー)を併用し、これらの臓器の形態や状態を確認します。腹部超音波検査は体への負担が少なく、痛みや被ばくの心配もない安全な検査です。
機能性ディスペプシアの治療とお薬
機能性ディスペプシアの治療は、患者様が満足できる症状の改善を目標とします。そのためには、信頼関係に基づいた良好な患者―医師関係が重要な役割を果たします。
生活習慣の改善
機能性ディスペプシアの患者様では、必要な睡眠が十分に確保されていなかったり、食事時間の不規則や野菜不足などの食習慣の乱れが見られることが多く、場合によってはお仕事にも影響が及びます。また、運動不足が関与することも報告されています。さらに、高カロリー・高脂肪食や喫煙が症状に悪影響を与えることも分かっています。
生活改善のポイントとしては、満腹になるまで食べず、少量を複数回に分けて摂ること、高脂肪食を避けること、禁煙、飲酒やコーヒーの摂取を控えることなどが挙げられます。これらを意識することで、症状の軽減や再発予防につながる可能性があります。
薬物療法
機能性ディスペプシアの薬物治療では、まず胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害薬〔PPI〕やH₂受容体拮抗薬〔H₂ブロッカー〕)の有用性が示されています。
さらに、アコチアミド(商品名:アコファイド)は胃の運動機能を改善し、胃もたれや早期飽満感などの症状軽減に効果があることが示され、機能性ディスペプシアの治療薬として初めて承認されました。
その他にも、ドパミン受容体拮抗薬(メトクロプラミド、ドンペリドン、スルピリド、イトプリド)、5-HT₄受容体作動薬のモサプリド、さらに六君子湯などの漢方薬も症状改善に有用と考えられています。
ピロリ菌除菌
ピロリ菌はウレアーゼという酵素を利用して周囲の尿素を分解し、アルカリ性のアンモニアを生成します。このアンモニアによって強酸性の胃酸を中和し、自らが生息できる環境を作り出して胃の中に定着します。しかし、この過程でアンモニアの毒性や炎症反応により胃粘膜が傷つき、炎症が慢性化します。こうした状態は機能性ディスペプシアの悪化に関与するとされ、H. pylori関連ディスペプシアと呼ばれます。
原因がピロリ菌である場合、除菌治療によって症状改善が期待できます。また、ピロリ菌は胃がんの原因にもなることが知られており、特に若年時の除菌は胃がん予防効果が高いとされています。高齢の方でも一定の予防効果が得られるため、年齢を問わず除菌治療は有効と考えられています。
機能性ディスペプシアを放置するとどうなる?
機能性ディスペプシアを放置して症状が悪化すると、日常生活や食事内容に制限が必要になることがあります。症状が長引くことで精神的ストレスが増し、うつ病などの精神疾患につながる可能性もあります。さらに、胃潰瘍や胃がんなども機能性ディスペプシアと似た症状を呈するため、早期に適切な検査や治療を受けられない場合、重篤な状態に進行する危険性があります。
このため、胃の不快感や痛みなどの症状が続く場合は、自己判断せず、できるだけ早めに消化器の専門医に相談することが大切です。