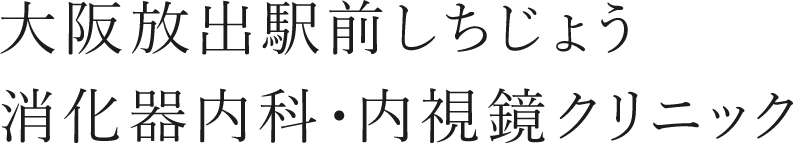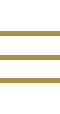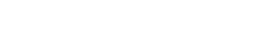慢性胃炎の症状をチェック
- 胃のむかつき、胃もたれ、不快感
- 胃の痛み、しくしくした感じ
- 胸焼け・吐き気
- 腹部膨満感(お腹の張り)
- ゲップ
- 食欲不振
上記の症状がある方は、慢性胃炎の可能性がありますので、一度当院までご相談ください。
慢性胃炎の原因はピロリ菌感染?
慢性胃炎は、胃の粘膜に炎症が長期間続く状態を指します。原因は多岐にわたりますが、主に以下のような要因が関与しています。
-
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)感染
幼少期に感染し、そのまま長期間持続すると、胃粘膜に慢性的な炎症が生じます。この炎症により胃粘膜が徐々に萎縮し、萎縮性胃炎と呼ばれる状態に進行することがあります。萎縮性胃炎は将来的に胃潰瘍や胃がんのリスクを高めることが知られています。日本の内視鏡専門医であれば、萎縮性胃炎の診断は概ね可能です。 -
薬剤による影響
鎮痛薬(NSAIDs)やステロイドなどの薬剤は、胃粘膜を刺激し、炎症やびらんを引き起こすことがあります。服薬歴の確認が重要です。 -
加齢や体質
ヘリコバクター・ピロリ感染に加えて、加齢に伴う胃粘膜の防御機構の低下も、粘膜の萎縮を進行させる一因となります。また、体質や遺伝的要因などによって、胃粘膜の状態には個人差が見られます。 -
ストレスや生活習慣の乱れ
過度のストレス、睡眠不足、偏った食生活、喫煙、過剰な飲酒などは、胃への負担となり、炎症を引き起こす要因となります。 -
自己免疫性胃炎
自身の免疫が誤って胃の粘膜を攻撃してしまう病気で、ビタミンB12の吸収障害や巨赤芽球性貧血の原因になることがあります。診断には専門的な知識と経験が必要です。
慢性胃炎を放置するとどうなる?

慢性胃炎は、胃の粘膜に炎症が長く続く状態です。症状が軽かったり自覚がなかったりすることも多いため、「様子を見よう」と思いがちですが、放置してしまうと次のようなリスクがあります。
- 胃の粘膜が弱くなり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を起こしやすくなる
胃の防御機能が低下し、粘膜がただれて潰瘍になることがあります。 - 萎縮性胃炎に進行する
ピロリ菌による慢性的な炎症が続くことで、胃の粘膜が薄くなり、胃液や消化酵素の分泌が低下します。消化不良や栄養吸収の低下の原因となります。 - 胃がんのリスクが上がる
特にピロリ菌に感染したまま放置している場合、長年の炎症によって胃がんのリスクが高まることが知られています。 - 貧血や体重減少につながることも
胃の働きが弱まることで、鉄やビタミンの吸収が悪くなり、慢性的な貧血を起こすこともあります。
慢性胃炎の検査
 まずは問診で、現在お困りの症状、服用中のお薬、普段の食生活などについて詳しくお伺いします。
まずは問診で、現在お困りの症状、服用中のお薬、普段の食生活などについて詳しくお伺いします。
必要に応じて、胃の粘膜の状態や、逆流性食道炎の有無などをリアルタイムで観察するために、胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)を行います。
特に、胃の粘膜が萎縮すると、胃がんのリスクが高くなることが知られています。胃カメラによって、こうした変化を早く見つけることで、胃がんの早期発見・早期治療が可能になります。
また、ピロリ菌に感染していると、胃の粘膜に慢性的な炎症が生じ、慢性胃炎(萎縮性胃炎)、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃がんなどの発症につながります。
特に日本では胃がんの原因の95%以上がピロリ菌感染によるものとされており、早期に感染を発見し除菌治療を行うことで、これらの疾患の発生リスクを下げることが可能です。
当院でも、苦痛の少ない胃カメラ検査を行っております。症状がある方はもちろん、健康チェックとしても検査を受けていただけます。気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
慢性胃炎は治りますか?治療方針は?
慢性胃炎の治療は、生活習慣の改善・ピロリ菌の除菌・お薬による治療(薬物療法)の3つを柱として進めていきます。
生活習慣改善
薬物療法によって症状が改善した後も、再発を防ぐためには生活習慣の見直しが不可欠です。生活リズムを整え、胃に負担をかけないよう心がけることで、慢性胃炎を再発しにくい状態へと導くことができます。
特に以下のような習慣がある方は、積極的に生活習慣の改善に取り組みましょう。
- 飲酒や喫煙の習慣がある
- 暴飲暴食をしがちである
- 脂肪分・塩分の多い食事を好む
- 野菜の摂取量が少ない
日々の積み重ねが胃の健康を左右します。継続的な取り組みが大切です。
ピロリ菌除菌
ピロリ菌感染が疑われる方へ
慢性胃炎の原因として、ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)菌の感染が疑われる場合には、まずピロリ菌検査を受けることをおすすめします。
陽性と診断された場合、除菌治療として、抗菌薬2種類と胃酸分泌抑制剤を1週間服用していただきます。
除菌治療の成功率と使用薬剤について
近年では、ボノプラザン(胃酸分泌抑制薬)と抗生物質を組み合わせた治療法が、従来のプロトンポンプ阻害薬(PPI)を用いた方法よりも除菌成功率が高いことが明らかになっています。
当院院長は、東京大学および関連施設においてこの治療法の有効性を報告しており、1回目の除菌成功率は87%でした(Shichijoら, Journal of Digestive Diseases, 2016)。この治療は保険適用内で受けることができます。
服薬から2ヶ月以上経過した後に判定検査を行い、除菌の成否を確認します。1回目で除菌が成功しなかった場合でも、2回目まで健康保険での治療が可能です。2回目までの治療での成功率は約98%と非常に高くなっています。
3回目の除菌治療について(自費診療)
2回目までの治療でも除菌が成功しなかった場合には、判定結果の確認を行ったうえで、3回目の除菌治療をご提案することが可能です。当院では、院長が東京大学で行った研究に基づき、シタフロキサシンを用いた治療を行っており、83%の成功率が報告されています(Hirata, Shichijoら, International Journal of Infectious Diseases, 2016)。
※この3回目の治療は自費診療となります。
除菌後の注意点:胃がんリスクと内視鏡フォロー
除菌治療に成功しても、萎縮性胃炎が高度に進行している方や、腸上皮化生(胃の粘膜が腸のように変化する状態)が認められる方では、胃がんの発症リスクが依然として高いことが報告されています。
院長は、東京大学で行った研究においてこのリスクについて明らかにしており(Shichijo, Hirata ら, Gastrointestinal Endoscopy, 2016)、また、日本消化器内視鏡学会『早期胃癌の内視鏡診断ガイドライン(第2版)』の作成委員としても、除菌後の定期的な内視鏡検査の重要性を強調しています。
そのため、除菌治療が成功した場合でも安心せず、継続的な内視鏡による経過観察が強く推奨されます。
(※なお、こうしたリスクがある場合であっても、除菌治療は胃がん予防の観点から積極的に行うべきとされています。)
専門医によるご説明
当院では、日本ヘリコバクター学会認定 H. pylori感染症認定医であり、「H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2024」作成に協力した院長が、ピロリ菌感染の診断・治療について専門的な立場からわかりやすくご説明いたします。
気になる症状がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ピロリ菌の発見でノーベル賞を受賞したマーシャル博士、AI medical serviceの多田智裕先生と
内視鏡画像から人工知能(AI)によってピロリ菌の感染の有無を判定する論文(Shichijo, Tadaら, EBioMedicine, 2017)の成果を世界で初めて国際学会で発表した際に(2017年、シカゴ)
お薬による治療(薬物療法)
胃酸の分泌を抑える薬や胃粘膜を保護する薬など、患者様一人ひとりの症状や状態に応じて、適切なお薬を使用します。市販薬で一時的に症状が改善することもありますが、胃がんなど重篤な疾患でも慢性胃炎と似た症状がみられることがあるため、早めに医療機関で検査と治療を受けることが大切です。
当院では、お忙しい方にもご利用いただけるようオンライン診療にも対応しております。少しでもご不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
慢性胃炎で摂りすぎに
注意したい食べものは?
慢性胃炎の方は、胃にできるだけ負担をかけないことが大切です。
そのためには、量を控えめにし、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
また、食事の際はよく噛んで、ゆっくりと時間をかけて食べることが、胃の負担を軽減するポイントです。
以下のような食品は胃に刺激を与えたり、消化に時間がかかったりするため、食べすぎないよう注意が必要です。
胃に負担がかかる食品の例

- 辛いもの:唐辛子、カレー、キムチ、ニンニクなど
- 酸味の強いもの:酢の物、柑橘類、梅干しなど
- 脂っこいもの:揚げ物、ラーメン、肉の脂身など
- 甘すぎるもの:チョコレート、生クリームたっぷりのケーキ、菓子パンなど
- アルコール類:ビール、ワイン、日本酒など
- カフェインを多く含むもの:コーヒー、濃いお茶、エナジードリンクなど
- 炭酸飲料:コーラ、炭酸水、サイダーなど
- 塩分の多いもの:漬物、梅干し、カップラーメンなどのインスタント食品、濃い味付けの料理など
- 冷たいもの:アイスクリーム、冷たい飲み物など
- 硬くて消化の悪いもの:ごぼう、れんこん、イカ、たこ、こんにゃくなど
胃にやさしい食事のポイント
- よく煮る・蒸す・茹でるなど消化しやすい調理法を選ぶ
- 食事はゆっくりよく噛んで食べる
- 食べ過ぎ・早食いを避ける
- 寝る直前の食事や飲酒は控える