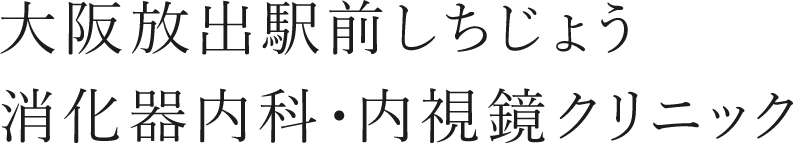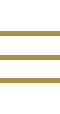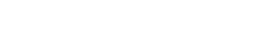尿蛋白を指摘されたときに知っておきたい、原因と注意点
尿蛋白とは
 尿検査で「尿蛋白(たんぱく尿)」を指摘されることがあります。健康な腎臓ではフィルターの働きにより、ほとんど尿には出ません。腎臓や尿路に異常が起こると、タンパク質が正常より多く尿に混じるようになります。
尿検査で「尿蛋白(たんぱく尿)」を指摘されることがあります。健康な腎臓ではフィルターの働きにより、ほとんど尿には出ません。腎臓や尿路に異常が起こると、タンパク質が正常より多く尿に混じるようになります。
蛋白尿が出る主な原因
一時的なもの(病気ではないケース)
一過性蛋白尿
健康な方でも、風邪や発熱、強い運動、ストレス、脱水などで一時的に出ることがあります。
男性では採尿の前日に射精がある場合、女性では月経中の検査の場合に偽陽性になることがあります。
起立性蛋白尿
立位や運動時にのみ尿にタンパクが出る良性の状態で、通常は横になって休むと出なくなります。特に若年者(10代から30代)にみられることが多く、成長とともに自然に改善することが一般的です。しかし他の腎疾患との鑑別が重要です。
病気が原因となる場合
腎炎
溶連菌感染後の急性糸球体腎炎や、ANCA関連腎炎など。
慢性腎臓病(CKD)
腎臓の機能が徐々に低下していく疾患の総称。腎機能が正常の60%以下に下がる、または蛋白尿が3か月以上続く場合に診断されます。
多発性嚢胞腎
腎臓に多数の嚢胞(液体の袋)ができて、腎臓の正常な部分が圧迫される病気です。
尿路結石(腎結石・尿管結石など)
強い痛みや血尿に伴って蛋白尿が見られることがあります。
尿路上皮がん(膀胱がんなど)
腫瘍からの出血により血尿とともに尿蛋白が出ることがあります。
尿路感染症(膀胱炎や腎盂腎炎など)
炎症によって血尿や蛋白尿が出ることがあります。
尿蛋白を予防・改善するには
蛋白尿が続く場合でも、早めの治療と生活改善によって腎臓の働きを守ることができます。
治療は、
- 原因となる病気に対する適切な治療(薬物療法など)
- 塩分を控える食事
- 体重管理(肥満は腎臓に負担をかけます)
- 血圧や血糖のコントロール
- 十分な水分補給と休養
当院では、検査結果をもとに原因や重症度を詳しく確認し、患者さんそれぞれに合った治療・生活指導を行っています。
「尿が濁っている」「泡立つ」「色が濃い」などの変化が続くときは、早めにご相談ください。
尿検査で「血尿」を指摘された方へ

尿に血液が混じっていると指摘された場合は、まず泌尿器科でのくわしい検査が必要です。最初は腹部エコー(超音波検査)を行い、必要に応じてCT・MR・採血膀胱鏡検査などを追加します。
※CTやMRIなど専門的な検査が必要な場合は、連携病院へご紹介いたします。
血尿とは
血尿とは、尿の中に血液が混じる状態です。痛みや違和感を伴うこともあれば、無症状で健康診断や検査で偶然見つかることもあります。
血尿の種類
顕微鏡的血尿
肉眼では見えませんが、顕微鏡で調べると赤血球が混ざっているものです。
肉眼的血尿
尿の色が赤っぽくなったり茶色に濁ったりして目で見てわかる血尿です。痛みや排尿異常を伴うこともありますが、無症状のこともあります。
血尿の原因となる主な病気
血尿はさまざまな原因で起こります。代表的なものは以下の通りです。
膀胱がん
血尿をきっかけに見つかることが多い腫瘍。初期は排尿時の違和感や頻尿を伴うこともあります。
尿管結石・腎結石
結石が尿路を通過するときに強い痛みや血尿が生じます。
前立腺がん
進行すると血尿や排尿障害(出にくい・残尿感など)がみられます。
膀胱炎・尿道炎
細菌感染により頻尿・排尿痛・血尿を伴うことがあります。
前立腺炎
前立腺肥大などに伴い炎症が起こると血尿を伴うことがあります。
腎盂・尿管がん
比較的まれですが、腫瘍からの出血で血尿が生じます。
突発性腎出血
明確な原因がなく突然腎臓から出血することがあります。多くは良性ですが、精密検査が必要です。
腎臓の病気(腎炎など)
腎臓に炎症や障害があると出血が起こることがあります。
原因不明
検査をしても明らかな原因が特定できないこともあります。悪性疾患を除外するため定期的な経過観察が行われます。
血尿の予防・改善のためにできること
食生活の工夫
肉類などの動物性たんぱく質や塩分・ビタミンCの摂りすぎは結石の原因となるため控えめにし、クエン酸(レモン・梅干しなど)を含む食品を取りましょう。アルコールは適量にし、水分をしっかり摂って尿を薄めることで、結石予防につながります。
感染予防
水分をこまめに摂り、トイレを我慢しないことが大切です。外陰部を清潔に保ち、生理用品は数時間ごとに交換しましょう。体を冷やさないよう温かい飲み物を選ぶことも効果的です。
定期的な健診
自覚症状がなくても血尿が出ていることがあります。年1回の健診や尿検査を受けることで早期発見・早期治療につながります。
尿意を感じたら早めにトイレ
尿意を無理に我慢すると膀胱や尿道に負担がかかり、感染症のリスクが高まります。尿意を感じたらできるだけ我慢せずに排尿しましょう。