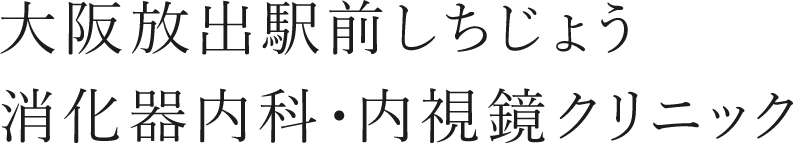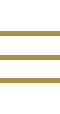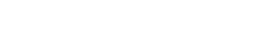- 過敏性腸症候群とは?主な原因は?
- 過敏性腸症候群の症状をチェック
- 過敏性腸症候群の種類
- 過敏性腸症候群の検査
- 過敏性腸症候群の治し方
- 過敏性腸症候群になった時の食べ物
(低FODMAP食) - 過敏性腸症候群を落ち着かせる・
和らげる方法は?
過敏性腸症候群とは?主な原因は?
どんな病気?
 過敏性腸症候群(IBS)は、お腹の不快感や痛みに加えて、便秘や下痢などの便通のトラブルが続く病気です。命に関わることはありませんが、「電車やバスでトイレに行けないのが不安」「仕事中もお腹の調子が気になって集中できない」といったように、生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。
過敏性腸症候群(IBS)は、お腹の不快感や痛みに加えて、便秘や下痢などの便通のトラブルが続く病気です。命に関わることはありませんが、「電車やバスでトイレに行けないのが不安」「仕事中もお腹の調子が気になって集中できない」といったように、生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。
診断について
国際的に使われているROME IV基準では、次のような条件を満たすと過敏性腸症候群(IBS)と診断されます。
- 症状が6か月以上前からある
- 最近3か月のうち、週1日以上の腹痛がある
- その腹痛が次のうち2つ以上に関連している
- 排便で症状が変わる
- 排便の回数が変わる
- 便の形(硬さややわらかさ)が変わる
なぜ起こるの?
過敏性腸症候群(IBS)は「機能性腸疾患」といわれ、腸に明らかな病気がなくても症状が出ます。
原因はひとつではなく、いくつかの要素が関係しています。
- ストレスと腸の関係(脳腸相関)
今はストレスがなくても若い頃までにストレスを受けていると発症しやすくなる - 腸内細菌のバランスの乱れ
- 腸の粘膜の炎症や透過性の変化
- 神経伝達物質(セロトニンなど)、ストレス関連ペプチドであるCRHといった内分泌物質の関与
- 遺伝的な体質
- 心理的な不安やうつ症状
どれくらいの人がかかる?
日本では約10人に1人が過敏性腸症候群(IBS)に悩んでいるといわれています。特に若い方や女性に多い傾向があります。
また、感染性腸炎にかかった方のうち、約10%がその後、過敏性腸症候群(IBS)を発症すると報告されています。特に女性や若い方、強いストレスや不安を抱えている方、重い胃腸炎にかかった方では、過敏性腸症候群(IBS)になりやすいことがわかっています。ただし、早めに相談いただければ症状を和らげる方法がありますので、安心してご受診ください。
過敏性腸症候群の症状をチェック
次のような症状が長く続いている方は、過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。
- 数か月にわたり下痢や便秘が続く
- 数週間から数か月にわたるお腹の痛みや不調
- 排便回数の異常(多すぎる・少なすぎる)
- 急な強い便意におそわれる
- 排便後も残便感がある
- ストレスで症状が悪化する
- 便の形が不安定な状態が続く
- 排便後に一時的に痛みがやわらぐ
- おならが増える(ガスがたまりやすい)
- 便に粘液が混じる
これらの症状は「気のせい」や「体質」ではなく、過敏性腸症候群という治療可能な病気のサインかもしれません。
お腹の症状が長引くと、生活や仕事、学業に支障をきたすこともあります。
気になる症状がある方は、どうぞ一人で悩まずご相談ください。
過敏性腸症候群の種類
症状の内容に応じて「便秘型」「下痢型」「混合型」「分類不能型」の4つに大別されます。
便秘型
- 排便の25%以上が硬便やうさぎの糞のような便(Bristol便形状スケール 1〜2)
- 下痢便(スケール6〜7)は25%未満
- 便秘に伴う腹部症状が主体
- 男性に多い

図 Bristol便形状スケール
下痢型
- 排便の25%以上が軟便・水様便(スケール6〜7)
- 硬便やうさぎの糞のような便は25%未満
- 朝方や食後の下痢、急な便意が特徴
- 女性に多い
混合型
- 排便の25%以上が硬便やうさぎの糞のような便、かつ25%以上が軟便
- 便形状が日によって大きく変化する
- 女性に多い
分類不能型
上記のいずれにも当てはまらない。
過敏性腸症候群の検査

過敏性腸症候群と似た症状は、実は他の消化器の病気でも起こります。
そのため、大腸カメラ検査・超音波検査・血液検査・尿検査などを行い、潰瘍性大腸炎や大腸がんなどの重大な病気を除外することが大切です。
次のような場合は、特に大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受けることをおすすめします。
- 発熱、関節痛がある
- 血便が出る
- 体重が減ってきた
- お腹や直腸にしこりを触れる
- お腹に水がたまっている(腹部の波動)
- トイレットペーパーに血がつく
- 50歳以上の方
- 大腸の病気にかかったことがある
- ご家族に大腸の病気をされた方がいる
- ご本人が「念のため調べておきたい」と思われる場合
- 採血・尿検査・腹部超音波検査で大腸の異常が疑われた場合
当院では、患者さまのご希望に応じて鎮痛剤や鎮静剤を使用し、経験豊富な内視鏡専門医が大腸カメラ検査を行っています。
苦痛を最小限に抑え、安心して検査を受けていただくために、大阪大学麻酔科 名誉教授・藤野裕士先生のご監修のもと、安全性に十分配慮した鎮静(静脈麻酔)を行っております。
検査中の不安や痛みをできる限り少なくするように配慮しておりますので、安心して受けていただけます。
過敏性腸症候群の治し方
過敏性腸症候群(IBS)は、生活習慣の改善と薬物療法を中心に治療を進めていきます。
命に関わる病気ではありませんが、症状が続くと生活の質(QOL)が下がってしまいます。適切に治療することで、日常生活を快適に過ごしていただくことを目標にします。
生活習慣の改善
飲食
規則的規則正しい食習慣を心がけましょう
- 1日3食、規則的に食事をとることが大切です。
- 水分は十分にとりましょう。特にカフェインを含まない温かい飲み物や常温の水分がおすすめです。
控えた方がよい食品
IBSの症状を悪化させることがある食品があります。個人差はありますが、次のような食品は注意が必要です。
- 脂っこいもの(揚げ物など)
- カフェイン飲料(コーヒー、紅茶、エナジードリンク)
- 香辛料を多く含む食品(唐辛子・カレー・胡椒・生姜・シナモン・ターメリックなど)
唐辛子の主成分「カプサイシン」は腸の動きを活発にし、腹部の不快感や痛みにつながるとされています。 - ミルクや乳製品(乳糖不耐症がある方は下痢を誘発することがあります)
下痢が多い方へ
- 下痢が続くと脱水になりやすいため、こまめに水分補給をしましょう。
- 冷たい飲み物は胃腸に負担をかけることがあるため、常温または温かい飲み物を選ぶのがおすすめです。
運動
過敏性腸症候群の症状は、適度な運動によって改善することが報告されています。
いきなり激しい運動をする必要はありません。まずは、
- 軽いウォーキング
- ストレッチ
- やさしい体操
といった無理のない運動から始めましょう。
徐々に習慣として続けられるようにすることが大切です。
薬物療法
生活習慣の改善だけでは症状が安定しない場合、薬による治療(薬物療法)を併せて行います。
IBSは症状のタイプ(下痢型・便秘型・混合型など)によって治療薬が異なります。当院では、患者さま一人ひとりの症状に合わせて、適切なお薬を選びます。
よく使われるお薬
- 水分を吸収あるいは保持して便通を調整するお薬(ポリカルボフィルカルシウム(商品名:ポリフル))
- 消化管の動きを整えるお薬(トリメブチンマレイン酸(商品名:セレキノン))
- お腹のけいれんを和らゲル薬(抗コリン薬(ブチルスコポラミンなど))
- 腸内環境を整える薬(乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌などのプロバイオティクス)
- 漢方薬(桂枝加芍薬湯)
- 食物繊維(オオバコ)
下痢型の場合
- 5-HT3拮抗薬(ラモセトロン(商品名:イリボー))
- 下痢止め(止痢薬、ロペラミド)
- 漢方薬(半夏瀉心湯)
便秘型の場合
- 便をやわらかくする薬(粘膜上皮機能変容薬(ルビプロストン(商品名:アミティーザ)、リナクロチド(商品名:リンゼス)))
- 腸の動きを助ける薬(エロビキシバット(商品名:グーフィス))
- 5-HT4刺激薬(慢性胃炎に対して用いられるモサプリド(商品名:ガスモチン)が有効という報告もあります)
- 非刺激性下剤(酸化マグネシウム(腎障害がある場合、使用に注意が必要)、ポリエチレングリコール(商品名:モビコール))
- 刺激性下剤(センナ、大黄、ビサコジル(商品名:テレミンソフト)、ピコスルファート):必要時のみ頓服で使用
- 漢方薬(大建中湯)
- 食物繊維(小麦ふすま)
過敏性腸症候群になった時の食べ物(低FODMAP食)

低FODMAP(フォドマップ)食とは、特定の発酵性の糖質(FODMAP)を控える食事法です。
FODMAPは腸内で発酵しやすく、水分を引き込みやすいため、IBS(過敏性腸症候群)の方ではお腹の張り・下痢・便秘・ガスの増加などの症状を悪化させることがあります。
FODMAPは以下の頭文字をとったものです
- Fermentable(発酵性)
- Oligosaccharides(オリゴ糖:小麦・玉ねぎ・豆類など)
- Disaccharides(二糖類:乳糖=牛乳やヨーグルトなど)
- Monosaccharides(単糖類:果糖=リンゴ・蜂蜜など)
- And
- Polyols(ポリオール=ソルビトール・キシリトールなどの人工甘味料、桃・さくらんぼなど)
低FODMAP食(食べてよい)
- 米、玄米、フォー、ビーフン、十割蕎麦
- ホウレンソウ、トマト、ダイコン、カボチャ、ジャガイモなどの野菜
- 牛肉、豚肉、鶏肉、魚、卵
- 木綿豆腐
- マーガリン、バター
- メープルシロップ
- 紅茶、緑茶
高FODMAP食(避けたほうが良い)
- 小麦製品(パン、うどん、パスタ、ラーメン、小麦そのもの):フルクタンが多い
- たまねぎ、長ネギ、ニラ、アスパラガス:フルクタンが多い
- 豆類(大豆、豆乳、納豆、ひよこ豆、レンズ豆):ガラクトオリゴ糖が多い
- サツマイモ:ソルビトールが多く高FODMAP(ただし少量なら可)
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム):乳糖が多い
- リンゴ:フルクトースが多い
- はちみつ:フルクトースが多い
- ミルクチョコレート:乳糖を含み高FODMAP
過敏性腸症候群を落ち着かせる・和らげる方法は?
過敏性腸症候群(IBS)は、日常生活の工夫によって症状が落ち着くことがあります。
ご自宅でできる工夫
- こまめに水分を摂る(常温または温かい飲み物がおすすめ)
- 食生活を整える(刺激物・脂っこい食事を控える)
- 軽い運動を習慣にする(ウォーキングやストレッチ)
- 睡眠時間をしっかり確保する
- お腹を温めたり、やさしくマッサージする
- 瞑想や深呼吸などでリラックスする
- ペパーミントオイルの使用(症状緩和に有効な報告があります)
- 鍼治療(体質改善やリラクゼーションにつながる場合があります)
放置するとどうなる?
IBS自体は命に関わる病気ではありません。
しかし、放置することで生活の質が大きく下がり、他の病気を合併しやすくなるといわれています。
関連が報告されている病気
- 消化管の病気:潰瘍性大腸炎、クローン病、逆流性食道炎、機能性ディスペプシア
- 慢性症状:線維筋痛症、慢性疲労症候群、慢性骨盤痛、顎関節症、間質性膀胱炎
- 女性に多い:月経前症候群
- 呼吸器:気管支喘息
- 心身の不調:不安や抑うつなどの精神症状
- 長期的には、認知症やパーキンソン病との関連、自殺リスクの増加も報告されています
「長引くから仕方ない」と思って放置すると、症状が悪化したり他の不調を合併してしまうことがあります。
過敏性腸症候群は治療や生活の工夫で改善できる病気です。
少しでも心当たりがある方は、どうぞお気軽に当院へご相談ください。