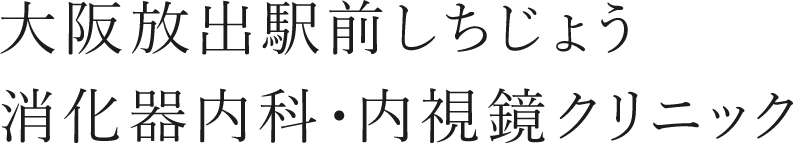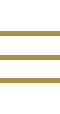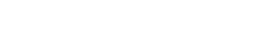- 当院の腎臓内科について
- 腎臓に不調が隠れているかもしれない症状
- 急性腎不全と慢性腎不全について
- 腎臓によくみられる疾患
- 水分不足には要注意!熱中症・脱水の予防ポイント
- 腎臓内科の受診から治療までの流れ
当院の腎臓内科について

近年、日本国内では慢性腎臓病(CKD)の患者数が増加しており、成人の約5人に1人、推定で2,000万人が罹患しているとされています。
CKDは初期段階ではほとんど症状が現れず、気づかないうちに腎機能が徐々に低下していく病気であり、放置すると末期腎不全に進行する可能性もあります。
当院では、腎臓の不調を抱える患者さまに対し、生涯にわたり寄り添った診療を大切にしています。
腎臓内科では、ネフローゼ症候群・慢性腎炎・多発性嚢胞腎などの腎疾患に対して、検査から診断、治療まで一貫して対応いたします。急性期の治療や、より高度な精密検査が必要な場合には、連携する専門医療機関をご紹介し、病状が安定した後は当院にて引き続き経過観察や治療を行うことが可能です。
また、タンパク尿や糖尿病、高血圧、肥満症といった生活習慣病は、腎機能の低下を引き起こす大きな要因となることがあります。これらの疾患の治療をすでに受けている方でも、腎臓への影響が心配な場合には、当院にて腎機能の評価や必要な検査・治療を並行して行うことが可能です。
将来的に透析治療が必要となる事態を避けるためにも、定期的に腎機能をチェックすることでCKDの早期発見と進行の予防に取り組むことが重要です。
腎臓に不調が隠れているかもしれない症状
腎臓の機能に異常がある場合、体にはさまざまなサインが現れることがあります。これらの症状は一見すると他の病気や体調不良と似ているため、見過ごされがちです。気になる症状が続くときは、放置せずに医療機関でのチェックをおすすめします。
だるさ・疲労感がなかなか取れない
風邪をひいていないのに全身がだるい、慢性的に疲れやすいといった症状が続く場合、腎機能低下による老廃物の蓄積や代謝異常が関係していることがあります。日常的にだるさが続くときは、腎機能を含めた検査を受けて原因を確認しましょう。
血圧が高いと言われた
腎機能が低下すると体内のナトリウムや水分をうまく排出できず、血液量が増えて血圧が上がります。高血圧が続くと心臓や腎臓の血管に負担がかかり、腎機能の悪化を招く悪循環に陥ることがあります。血圧の管理とともに腎臓のチェックも併せて行うことが大切です。
顔や手足のむくみ
腎機能が低下すると、余分な水分や塩分が体内に溜まり、むくみが生じます。特にまぶたや顔、手の甲、足の甲やすねなどに現れやすいのが特徴です。原因がはっきりしないむくみが続く場合は腎疾患の可能性があります。さらに重度の場合、肺に水が溜まり呼吸困難を引き起こすこともあり、注意が必要です。
尿の量や色の変化
腎臓の状態は尿に表れやすく、次のような変化が見られることがあります。
- 尿の回数や量が極端に増える/減る
- 尿が泡立つ(タンパク尿)
- 赤みがかった尿(血尿)
- 濁った尿や浮遊物が見られる
これらは、腎炎、尿路感染症、結石、腎臓がんなどのサインである可能性もあるため、注意が必要です。
健康診断で尿蛋白と判定された
健康診断で「尿蛋白(+)」と記載された場合、腎臓から本来排出されないはずのタンパク質が尿に漏れ出ている状態を意味します。これは腎炎や何らかの要因で腎臓に負担がかかっている可能性を示しており、放置せずに専門的な検査を受けることが重要です。原因によって治療法も異なるため、早めの対応が勧められます。
健康診断で尿潜血と判定された
尿検査で「尿潜血(+)」と判定されるのは、尿に赤血球が混じっている状態です。
これは「血尿」と呼ばれ、以下の2つに分けられます。
- 顕微鏡的血尿(目には見えないが検査で判明)
- 肉眼的血尿(目に見えて尿に赤みがある)
顕微鏡的血尿は糸球体腎炎などの腎疾患、肉眼的血尿は結石や感染症、腫瘍などが関与している可能性があるため、早期の精密検査が推奨されます。
クレアチニンやeGFRの異常値
血液検査で「クレアチニン値」や「eGFR(推算糸球体濾過量)」が異常と判定された場合、腎機能が低下している可能性があります。
- クレアチニン:筋肉の代謝産物で、腎臓で排出されます。高値は腎機能低下を示唆します。
- eGFR:血液をろ過する腎臓の能力を数値化したもので、低下しているほど腎機能が落ちています。
- BUN(血清尿素窒素)も併せて見ることで、より正確な評価が可能です。
これらの値に異常があった場合、専門的な評価と継続的なフォローが必要となります。
急性腎不全と慢性腎不全について
腎不全とは、腎臓の働きが大きく損なわれ、体に不要な水分や老廃物、毒素などを尿としてうまく排出できなくなった状態をいいます。一般的には、正常な腎機能の30%以下まで低下したときに腎不全と呼ばれます。その原因は多岐にわたります。
腎不全には急性と慢性の2つのタイプがあります。
急性腎不全は、数時間から数日の短い期間で腎臓の働きが急激に落ちるものです。尿がほとんど出なくなる(乏尿)、まったく排尿できなくなる(無尿)といった症状が突然みられることがあります。
慢性腎不全は、初期には目立った症状が出にくく、数か月から数年かけてゆっくり進行していきます。体に水分が溜まることでむくみが出るほか、全身の倦怠感や疲れやすさ、食欲不振、皮膚のかゆみ、夜間の頻尿などが現れることもあります。
腎臓によくみられる疾患
高血圧性腎症(こうけつあつせいじんしょう)
高血圧は全身の血管に負担をかけ、腎臓の血管にも動脈硬化を起こし、ダメージを与えます。その結果、腎臓の働きが悪くなることがあります。これを防ぐには血圧を適切にコントロールすることが大切です。血圧の薬にはいろいろな種類があり、作用の仕組みや副作用も異なるため、患者様それぞれに合った薬を選ぶことが重要です。現在治療を受けている方で「この薬で大丈夫かな」と感じる方は、早めにご相談ください。
糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)
糖尿病が原因で、腎臓の働きが少しずつ悪くなっていく病気です。日本では人工透析が必要になる原因の中で最も多い病気です。初期は尿に少しタンパクが出るだけですが、進行するとむくみや大量のタンパク尿が現れ、さらに悪化すると腎不全になることもあります。糖尿病性腎症では神経障害や網膜症を併発することも多く、血糖・血圧のしっかりした管理に加え、食事や運動の見直しが大切です。
腎炎(IgA腎症など)・ネフローゼ症候群
腎臓のフィルターの役割をしている「糸球体(しきゅうたい)」に炎症が起こる病気です。健康診断で血尿やタンパク尿を指摘され、見つかることがよくあります。中でも、尿に大量のタンパクが漏れ出す状態を「ネフローゼ症候群」と呼び、腎不全・心不全・血栓・感染症などの合併症のリスクもあります。原因は人それぞれ異なるため、必要に応じて専門病院と連携しながら治療を進めます。診断後も、当院で継続してサポートが可能です。
急性腎障害(急性腎不全)
数時間〜数日のうちに腎臓の働きが急に悪くなる状態です。尿量が減り、体内の老廃物や水分・塩分の調整ができなくなります。脱水や出血による腎血流の減少(腎前性)、腎臓そのものの炎症(腎性)、尿路閉塞(腎後性)などが原因です。特に高齢の方や、慢性腎臓病を持つ方に起こりやすく、要注意です。早めに見つけて治療すれば、回復も期待できますが、慢性腎不全へ移行するケースもあるため注意が必要です。
腎性貧血(じんせいひんけつ)
腎臓は、赤血球をつくる働きを促すホルモン「エリスロポエチン」を出しています。腎機能が低下するとこのホルモンが減って貧血が起こります。これは「鉄分不足」が原因の貧血とは違い、鉄剤だけでは改善しません。必要に応じて、エリスロポエチンを補う注射薬や産生を促す内服薬などによる治療が必要です。
薬による腎障害(薬剤性腎障害)
一部の薬は腎臓に負担をかけることがあります。よく知られているものでは、鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン、ボルタレンなど)や、一部の抗菌薬、高血圧の薬などがあります。治療では原因となる薬を特定して、使用を中止または減らすことが基本です。薬を飲んでいて「なんだか体調が悪い」と感じたときは、早めに医師に相談しましょう。
多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)
腎臓にたくさんの袋(嚢胞)ができて腎臓を圧迫し、腎臓の働きを徐々に失わせる遺伝性の病気です。最近は進行を抑える新しい薬も登場しています。早く見つけて治療を始めれば、透析に進むリスクを下げることが可能です。
水分不足には要注意!熱中症・脱水の予防ポイント

水分が不足すると、体温を調整がうまくできず、熱中症になりやすくなります。真夏の屋外だけでなく、湿度が高い室内でも発症することがあります。
特に高齢者や子どもは、のどの渇きを感じにくいため、意識してこまめに水分をとることが大切です。
また、電気代を気にしてエアコンを使わない方もいますが、暑い室内で過ごす間に熱中症になることもあります。室温を適切に保つことも大切な予防のポイントです。
医療機関の受診を考えるべき症状
次のような症状がある場合には、放置せず早めに医療機関を受診してください。
- めまいやふらつき
- 吐き気や嘔吐
- 普段とは違う、強い頭痛がある
- なんとなく気分が悪い(悪心)
- 熱が出て体温が高くなっている
- 大量の発汗、または全く汗が出ない状態
- 失神した、または熱で意識を失った
- けいれん(熱性けいれんを含む)
- 高体温に伴う疲労感(熱疲労)
- 意識がもうろうとする
これらの症状は、熱中症や脱水、脳や心臓などの深刻な異常が関係していることがあります。放置すると重症化する危険があるため、自己判断せずに早めに医療機関へご相談ください。
腎臓内科の受診から治療までの流れ
1診察
まず、問診票の内容をもとに、医師が現在の症状やこれまでの病気の経過などを詳しくお伺いします。そのうえで診察を行います。
2検査
必要に応じて、血液検査・尿検査・腎臓のエコー検査(超音波検査)などを行います。腎臓の状態を正確に把握するため、一般的な検査に加えて複数の項目を確認することがあります。気になることや不安な点があれば、遠慮なく医師にご相談ください。
3検査結果のご説明
当日わかる結果については、その場で医師がご説明します。一部の検査は結果が出るまでに数日かかる場合があり、その際は後日改めてご来院いただくことがあります。
4診断と治療
診察や結果をもとに、医師が診断を行い、適切な治療方針をご提案します。さらに詳しい検査や専門的な治療が必要と判断された場合には、専門医療機関をご紹介します。症状が落ち着いた後は、当院で継続的に経過をフォローすることが可能です。
※腎臓エコー検査(超音波検査)は、腎臓の状態を画像で確認する検査です。痛みはなく、放射線による被曝もありませんので安心して受けられます。血液検査や尿検査で腎機能の低下が疑われたときに行うことが多く、自己負担3割の場合の費用は1,500~2,000円程度です。