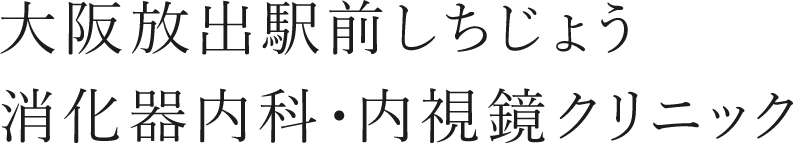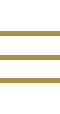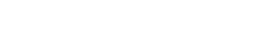便潜血検査とは
 便潜血検査は、便の中に血液が混じっていないかを調べる検査です。
便潜血検査は、便の中に血液が混じっていないかを調べる検査です。
現在、日本では免疫学的便潜血検査(FIT)が標準となっており、ヒトのヘモグロビンに特異的な抗体を用いるため、食事制限が不要で精度が高いのが特徴です。
ただし、食道・胃・十二指腸などの上部消化管からの出血は、消化液でヘモグロビンが分解されるため、検出されにくいことがあります。
便潜血検査は、日本で最も多いがんである大腸がんのスクリーニング検査として、健康診断などで広く実施されています。特に2日法(2回採便)が推奨されており、1回でも陽性なら大腸カメラ検査を受けることが推奨されます。
欧米では内視鏡検査を一次スクリーニングとして導入する国もあり、米国では大腸がん死亡率の低下が報告されています。日本では現状、FITが中心ですが、便潜血検査による受診者の追跡研究からも大腸がん死亡率を有意に減らす効果が証明されています。
ただし、便潜血で陽性となった方のうち、実際に大腸カメラを受ける割合は全国平均でも約60%にとどまっており、大阪府はそもそも検診受診率が低いのが課題とされています。
便潜血検査が陽性だったら?
 便潜血検査で陽性となった場合、大腸がんを含む消化器の病気で出血が起きている可能性があり、放置するのは危険です。
便潜血検査で陽性となった場合、大腸がんを含む消化器の病気で出血が起きている可能性があり、放置するのは危険です。
便潜血検査は、便をスティックで採取するだけの負担が少ない検査で、健康診断などで大腸がんのスクリーニングとして広く行われています。
通常、食べ物が便になる過程で血液が混ざることはありません。したがって、陽性という結果が出た場合は、大腸がんやポリープなどの病変が存在するサインである可能性が高いと考えられます。
実際に、便潜血検査で陽性となったにもかかわらず精密検査(大腸カメラ)を受けずに放置すると、大腸がんが新たに発生したり、進行した状態で見つかるリスクが増えることが報告されています(Lee YCら Clin Gastroenterol Hepatol 2019、Corley DAら JAMA 2017)。
一方で、便潜血陽性の段階で大腸カメラを受けて早期に発見・治療すれば、進行する前に完治できる可能性が高まることも示されています(Meester RGら Clin Gastroenterol Hepatol 2016)。
したがって、便潜血検査が陽性となった方は必ず消化器内科を受診し、大腸内視鏡検査を受けることが重要です。
なお、2日法で1回だけ陽性だった場合でも精密検査が必要ですので、安心せずにご相談ください。
便潜血検査が2回とも陽性だと
大腸がんの可能性は高い?
便潜血検査で1回陽性と2回陽性の違い
便潜血検査(2日法)では、1回だけ陽性の場合と2回とも陽性の場合で、大腸がんが見つかる確率に差があります。
- 1回だけ陽性
大腸カメラで大腸がんが見つかる確率は 約3〜5% とされています。 - 2回とも陽性
大腸がんが見つかる確率は 約5〜10% に上昇します。
このように、2回とも陽性の場合は大腸がんのリスクがより高くなるため、必ず大腸内視鏡検査を受けることが大切です。
便潜血検査が陽性で
考えられる病気
実際には、便潜血検査が陽性になる原因はさまざまで、大腸がん以外の病気や良性の疾患によっても出血が起こります。
大腸がん
大腸がんとは、大腸に発生する悪性腫瘍です。大腸の粘膜にがんが生じると、便が通過する際や大腸の蠕動運動によって腫瘍と接触し、出血が起こることがあります。
このため、便に血液が混じっていないかを調べる便潜血検査は、大腸がんを早期に見つけるための重要なスクリーニング検査として広く行われています。
ただし、大腸がんは常に出血しているわけではありません。出血が少ないタイミングで採便すると、がんがあっても便潜血検査が陰性となることがあります。したがって、便潜血が陰性であっても、大腸がんを完全に否定できるわけではありません。
便潜血検査の精度について
便潜血検査(2日法)の大腸がん検出率は、研究から次のように報告されています。
- 早期がん:検出率 約50〜70%
- 進行がん:検出率 約80〜90%
一方で、2回とも陰性であれば進行がんの可能性は低いと考えられますが、完全に否定はできません。特に右側結腸の病変や出血を伴わないタイプの大腸がんは、便潜血検査で見逃されることがあります。
大腸がんで見られる症状
便潜血検査が陽性になるほか、次のような症状が大腸がんのサインとなる場合があります。
- 便通異常(便秘や下痢の繰り返し)
- 細い便が続く
- 腹痛
- 腹部膨満感
- 原因不明の体重減少
ご相談の目安
便潜血検査が陰性でも、上記のような症状がある場合には、大腸がんや他の消化器疾患の可能性があります。
少しでも気になる症状がある方は、なるべく早めに当院へご相談ください。
大腸ポリープ
大腸ポリープとは、大腸の粘膜が隆起してできる病変の総称です。
大きく 腫瘍性ポリープ と 非腫瘍性ポリープ に分けられ、腫瘍性ポリープはさらに良性と悪性(がん化したもの)に分けられます。
良性の腫瘍性ポリープでも、放置すると徐々に大きくなり、一部は悪性化して大腸がんへと進展することがあるため、見つかった場合は切除することが推奨されます。
ポリープと便潜血検査の関係
便がポリープと接触することで出血が起こる場合があり、その結果、便潜血検査が陽性になることがあります。便潜血検査で陽性となった方のうち、約30〜40%で大腸ポリープが発見されると報告されています。そのため、便潜血検査は大腸ポリープを発見するきっかけとしても重要な役割を果たします。
特に「大腸腺腫」と呼ばれるタイプのポリープは、大腸がんの前段階と考えられており、切除することで大腸がんの発生を予防できることが明らかになっています(National Polyp Study, Winawer SJ et al, N Engl J Med 1993; 329:1977–81)。
当院の院長は、これまでに10,000個以上の大腸ポリープを切除してきた実績があり、他の医療機関では切除が難しかった症例や、十分に切除されずに再発したポリープ・がんの治療経験も豊富です。内視鏡で届く範囲のポリープであれば、基本的にはその場で切除が可能です。ただし、大きさが20mmを超えるものや、体調・ご希望によっては、入院治療が望ましいケースもあります。そのような場合には、大阪国際がんセンターなどの専門医療機関と連携して、スムーズにご紹介いたしますので、どうぞご安心ください。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症や潰瘍が生じる病気です。明確な発症原因はまだ分かっていませんが、自己免疫の関与や腸内細菌との関連が指摘されており、厚生労働省から指定難病として認定されています。
症状と診断のきっかけ
炎症や潰瘍があると、わずかな刺激でも粘膜から出血しやすくなります。そのため、以下のような症状が出ることがあります。
- 腹痛
- 下痢
- 血便
多くの場合、これらの症状をきっかけに大腸カメラ検査を受け、診断に至ります。
一方で、軽症例では自覚症状が乏しいこともあり、便潜血検査が陽性になったことを契機に発見されるケースも少なくありません。
潰瘍性大腸炎は増加傾向
潰瘍性大腸炎の患者数は近年増加傾向にあります。早期発見・適切な治療によって、症状のコントロールや合併症の予防が可能になります。
便潜血検査で陽性になった場合、がんだけでなく潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患が隠れている可能性もあります。
便潜血検査で陽性と出た方は、ぜひ一度当院へご相談ください。
痔
痔は肛門周囲でよくみられる病気で、大きく次の3つに分類されます。
- いぼ痔(痔核)
直腸と肛門の境目より内側にできるものを「内痔核」、外側にできるものを「外痔核」といいます。 - 切れ痔(裂肛)
排便の際に肛門の皮膚が切れたり裂けたりして痛みや出血が起こる病気です。 - 痔ろう
肛門と直腸の間で細菌感染が起こり、膿がたまったあとにトンネル状の管ができる状態です。
便潜血検査と痔の関係
いぼ痔や切れ痔では排便時に出血することがあるため、便潜血検査で陽性になることがあります。ただし、「痔があるから安心」と思い込むのは危険です。痔による出血と、大腸がんや大腸ポリープなど深刻な病気による出血が区別できないためです。
受診のすすめ
痔はデリケートなお悩みで、受診をためらわれる方も少なくありません。しかし、放置すると悪化して日常生活に支障をきたすことがあります。
当院では、鶴見区でも数少ない大腸肛門病専門医が診察を行っています。症状に合わせて適切な治療をご提案いたしますので、安心してご相談ください。
便潜血検査が陽性だった方は
大阪市鶴見区の当院へ
当院では、日本消化器病学会・日本消化器内視鏡学会・日本大腸肛門病学会の専門医が、便潜血検査で陽性となった方に対して精密検査(大腸カメラ)を行っています。
便潜血検査で陽性となった場合、大腸がんやポリープなど重篤な病気が隠れている可能性があるため、必ず大腸カメラ検査を受けることが大切です。
また、便潜血検査が陰性であっても、
- 血便
- 黒色便
- 腹部の膨満感
- 腹痛
- 下痢や便秘の持続
といった症状がある場合には、大腸疾患が隠れている可能性があります。
症状があるときは陰性でも安心せず、なるべく早めに当院へご相談ください。